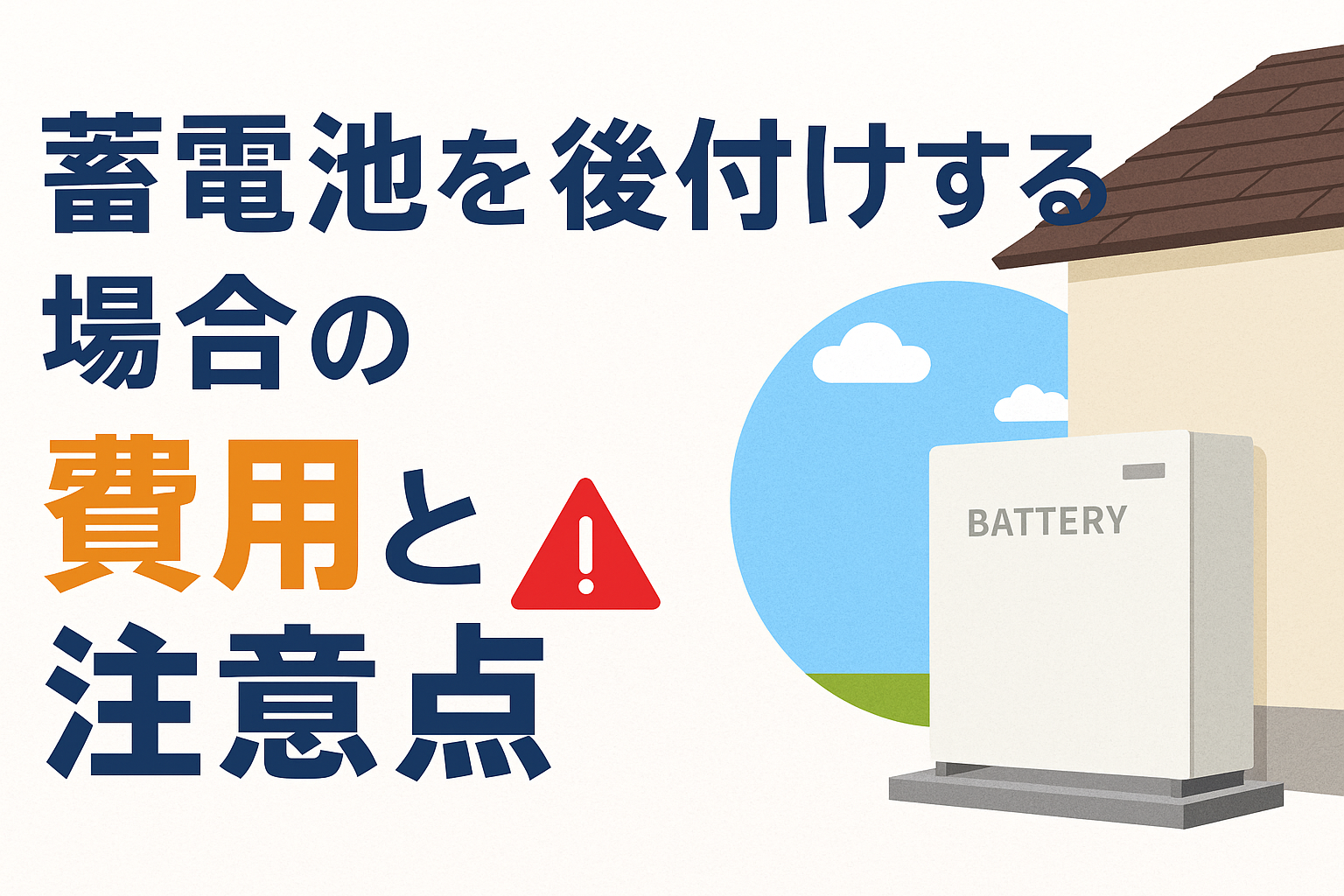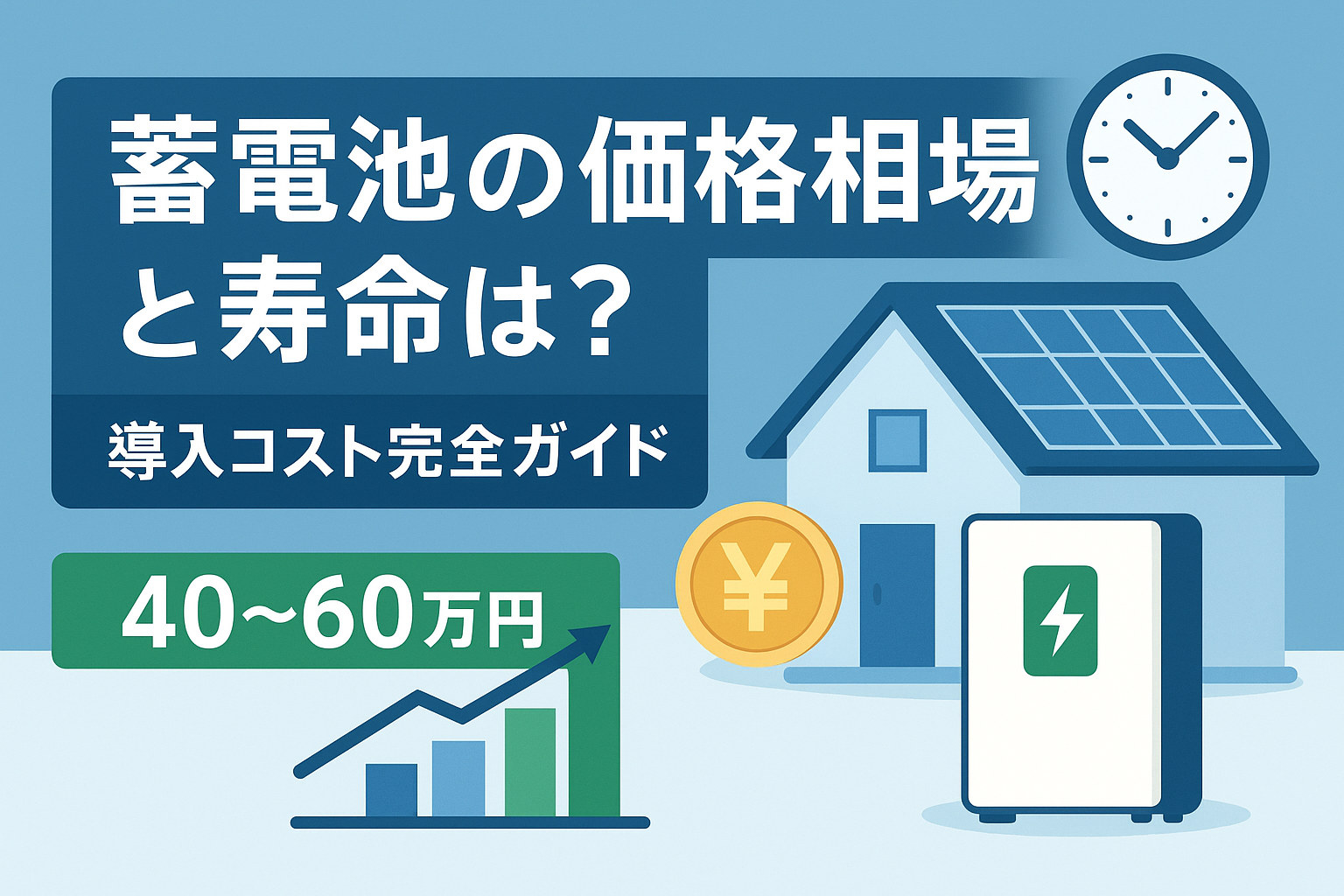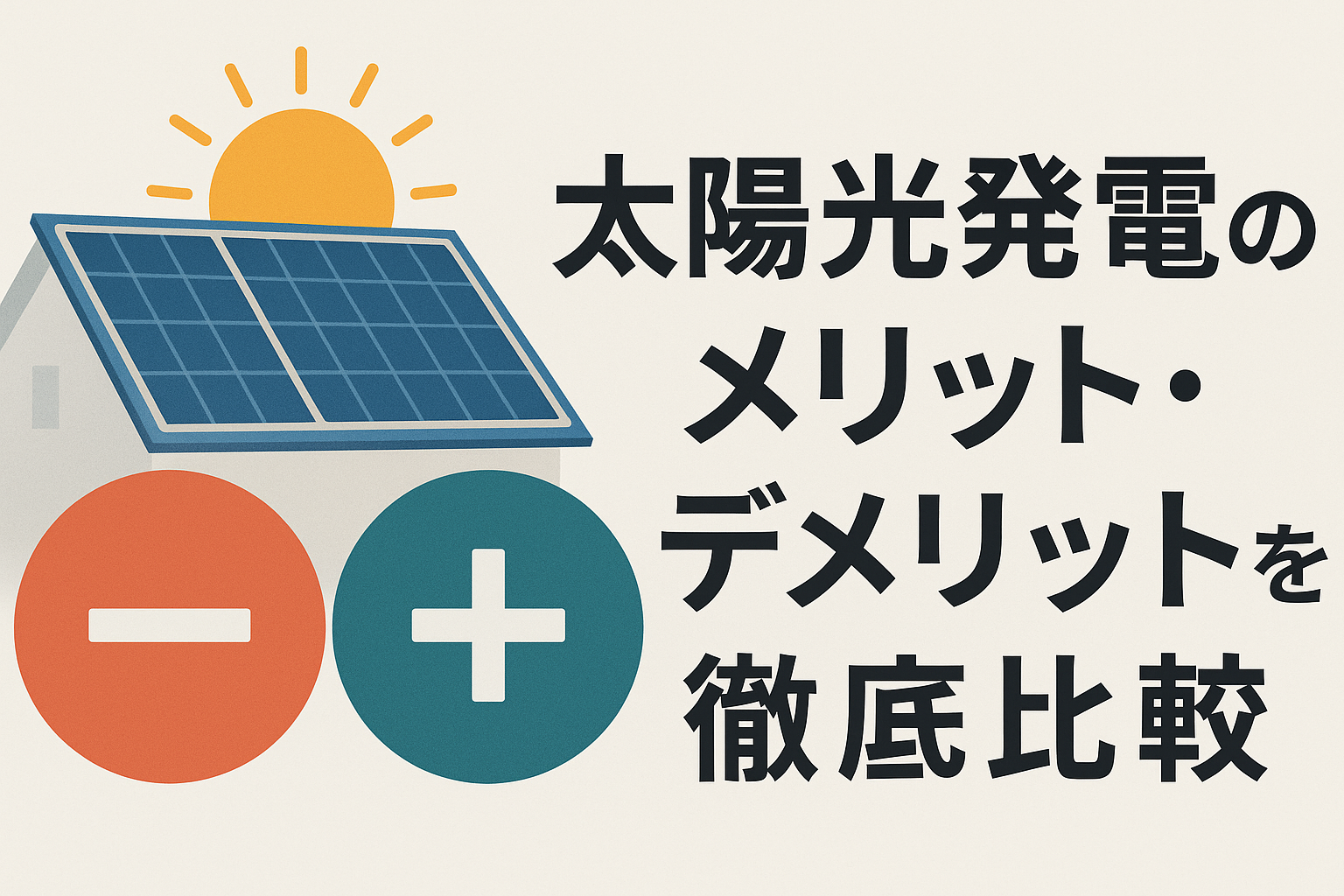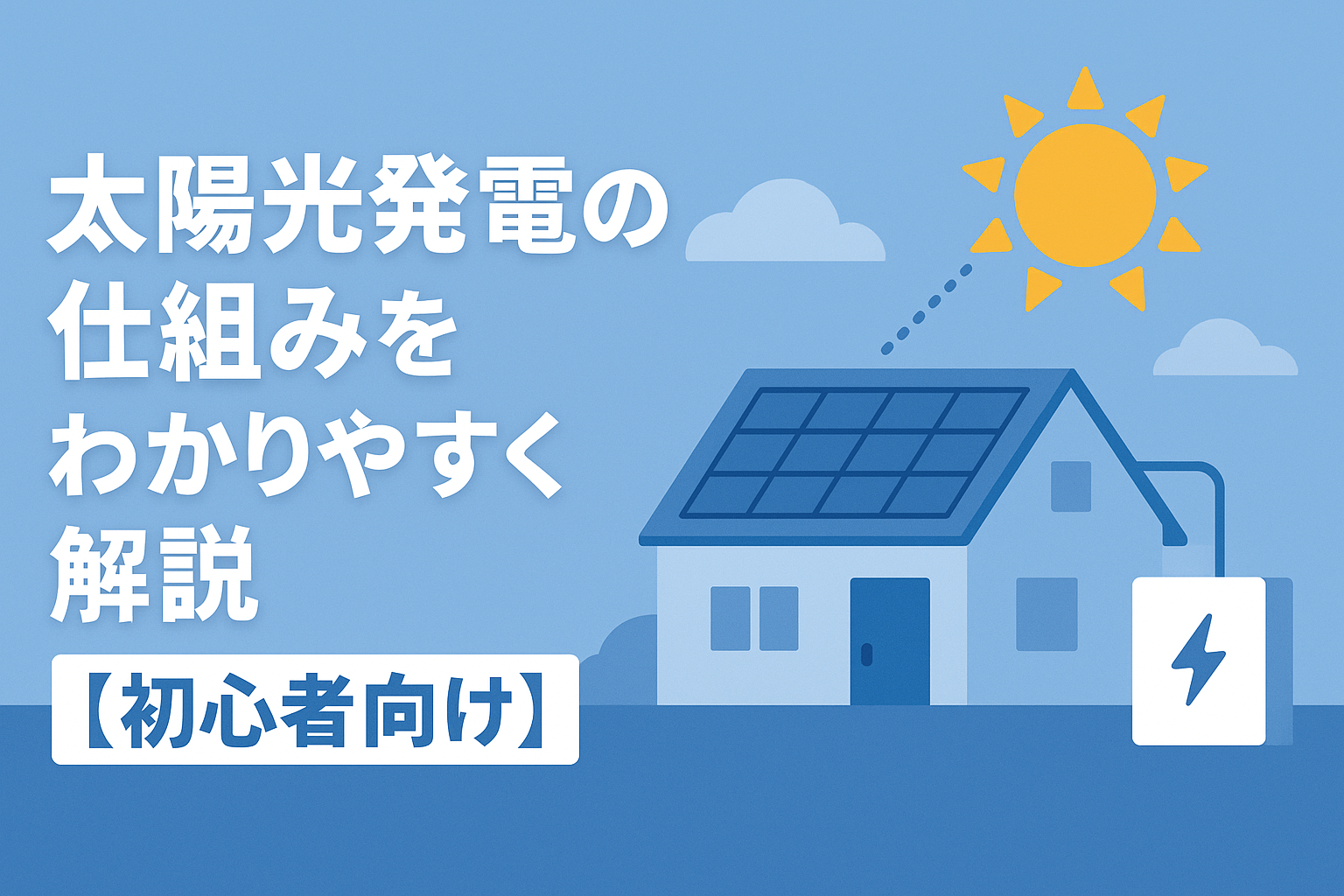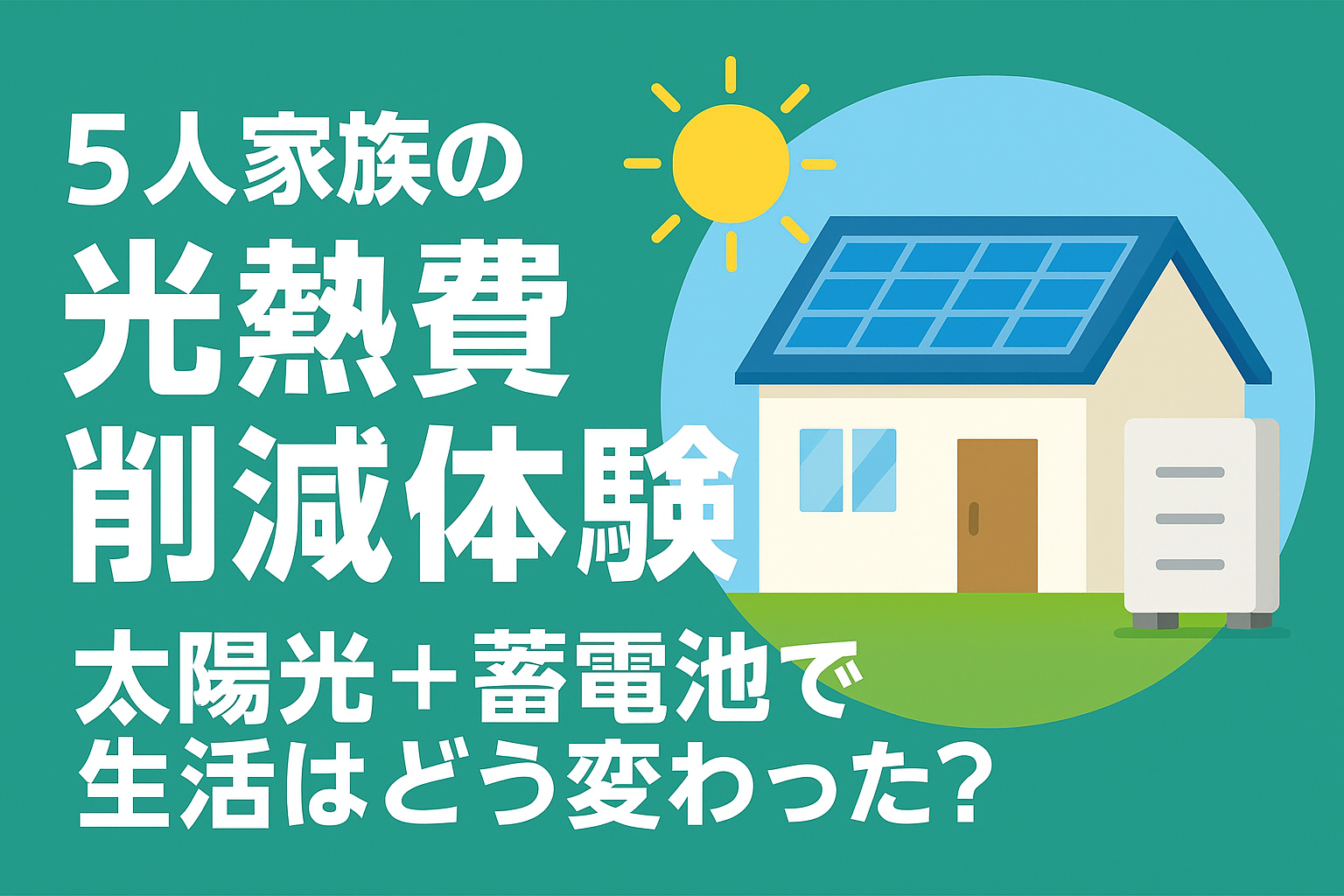地震や台風などの自然災害による停電は、いつ起こるかわかりません。そんなとき、太陽光発電と蓄電池の組み合わせが家庭を守る強力な備えになります。本記事では実際の停電時に「太陽光+蓄電池」がどう役立ったのか、リアルな事例とともに解説します。
災害時に停電が起こるとどうなる?
停電は私たちの生活を一瞬で不便に変えてしまいます。とくに長時間に及ぶ場合は、電気が使えないことが命に関わるリスクにもなり得ます。
- 冷蔵庫が止まり食材が傷む
- スマホの充電ができず情報収集が困難になる
- 冷暖房が使えず、熱中症や低体温症のリスクが高まる
- 電気ポットやIH調理器が使えず、食事の準備が難しい
- 在宅医療機器(酸素濃縮器や吸引器など)が停止する危険
こうした不便さやリスクを回避するために、災害時の電源確保は家庭にとって非常に重要です。
太陽光+蓄電池が災害時に強い理由
太陽光発電と蓄電池の組み合わせは「電気の自給自足」を可能にします。日中は太陽光で発電し、余った電気を蓄電池に充電。夜間や停電時には蓄電池から電気を取り出せるため、ライフラインを維持できるのです。
1. 日中の発電
停電中でも太陽が出ていれば発電が可能。蓄電池と連携していれば、発電した電気をそのまま家庭で使えます。
2. 夜間の電力供給
昼間に充電した電力を夜に使用できるため、照明や冷蔵庫、通信機器を稼働させられます。
3. 非常用コンセント
多くの蓄電池やハイブリッドパワコンには「非常用コンセント」があり、災害時でも一定の家電が稼働できます。
実際の事例①:地震による停電で助かった家庭
2021年の福島県沖地震では、一部地域で数日間の停電が発生しました。太陽光+蓄電池を導入していたAさん宅は、以下のように電気を活用できました。
- 冷蔵庫を24時間稼働させ、食材を無駄にせずに済んだ
- 夜間はLED照明を使い、安全に避難生活を送れた
- 蓄電池を通じてスマホやタブレットを充電し、情報収集や家族との連絡に不安がなかった
Aさんは「蓄電池があったおかげで不安がかなり軽減された」と話しています。
実際の事例②:台風による大規模停電での活用
2019年の台風15号では、千葉県を中心に数十万世帯が停電しました。Bさん宅は太陽光と9.8kWhの蓄電池を導入しており、停電中もほぼ普段通りの生活ができたといいます。
- エアコンは控えたが、扇風機と冷蔵庫は常時稼働
- IHではなく電気ポットでお湯を沸かし、簡単な調理を継続
- 電気自動車(EV)への充電も一部可能だった
停電が1週間以上続いた地域でも、Bさん宅は近隣住民にスマホ充電を提供するなど「地域の電源ステーション」として活躍しました。
実際の事例③:医療機器を支えた蓄電池
在宅医療を受けていたCさん宅では、蓄電池が命を守る存在となりました。Cさんは在宅酸素療法を利用しており、停電時に酸素濃縮器が止まれば生命に関わるリスクがあります。
- 蓄電池を使って酸素濃縮器を24時間稼働
- 太陽光発電により日中は電力を補給
- 医療機器の安定稼働により、入院を避けられた
このように、災害時の電源確保は命を守ることにも直結します。
蓄電池の容量と災害時の安心感
停電時にどの程度の生活ができるかは、蓄電池の容量で決まります。
- 4kWh前後:冷蔵庫・照明・スマホ充電程度
- 6~10kWh:冷蔵庫+照明+通信機器+炊飯器など
- 10kWh以上:冷暖房や医療機器も稼働でき、ほぼ普段通りの生活
災害対策を重視するなら、6kWh以上の蓄電池が推奨されます。
導入前に知っておくべき注意点
停電時に確実に電気を使うためには、以下の点に注意が必要です。
- 停電対応型か確認
すべての太陽光・蓄電池が停電対応ではないため、事前に機能をチェック。
- 分電盤の切替工事
家全体に電力を供給するタイプか、一部の回路のみかで利便性が変わります。
- 容量と使用時間のシミュレーション
災害時にどの家電を優先するかを考え、それに見合った蓄電池を選ぶ必要があります。
まとめ:災害時の安心を得るために
実際の事例を見てもわかるように、太陽光発電と蓄電池の組み合わせは「停電に強い家づくり」の鍵となります。電気の自給自足は日常の電気代削減だけでなく、非常時のライフライン確保にも直結するのです。これから太陽光や蓄電池の導入を検討している方は、補助金制度や一括見積もりを活用し、自宅に最適なシステムを選んでみてください。