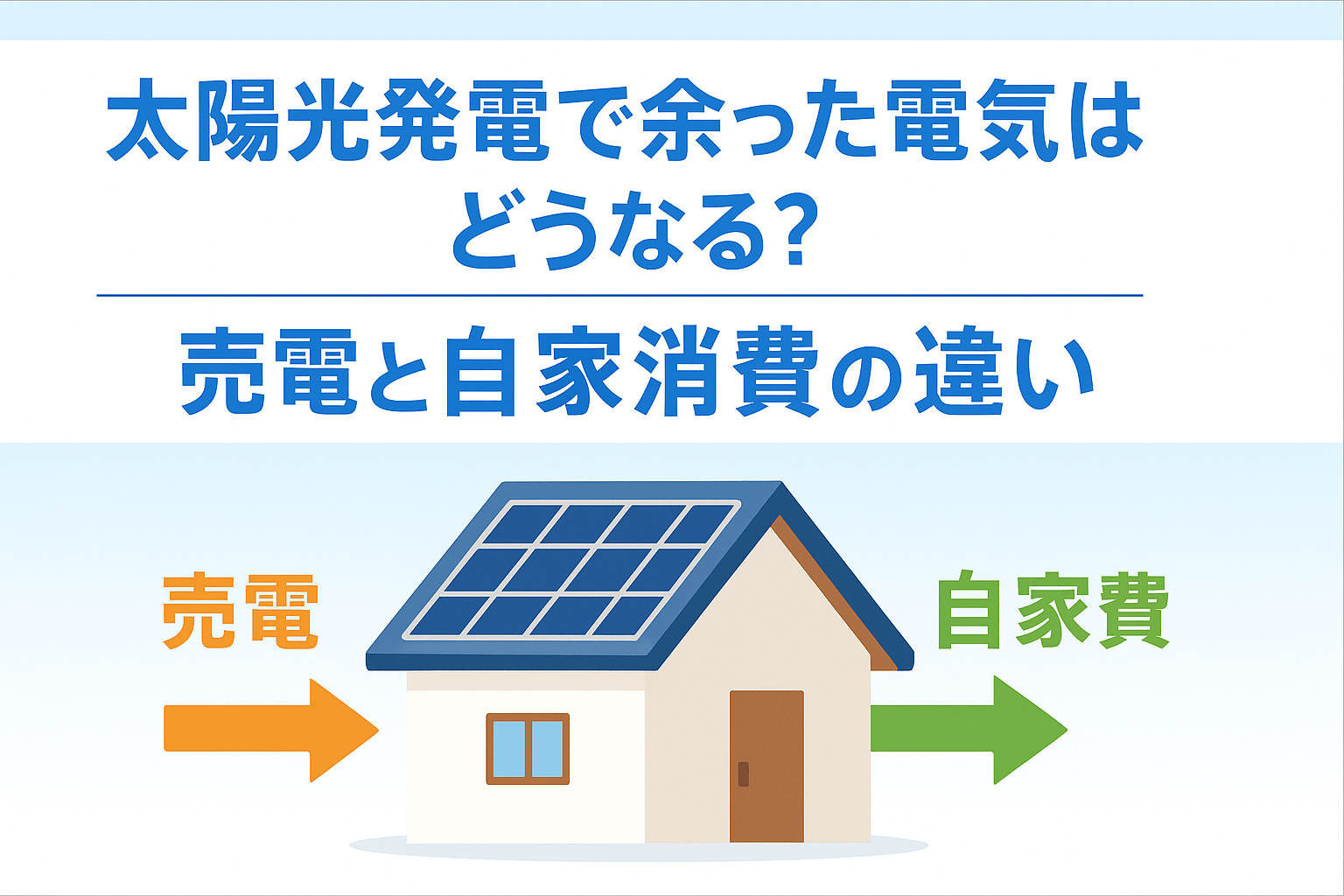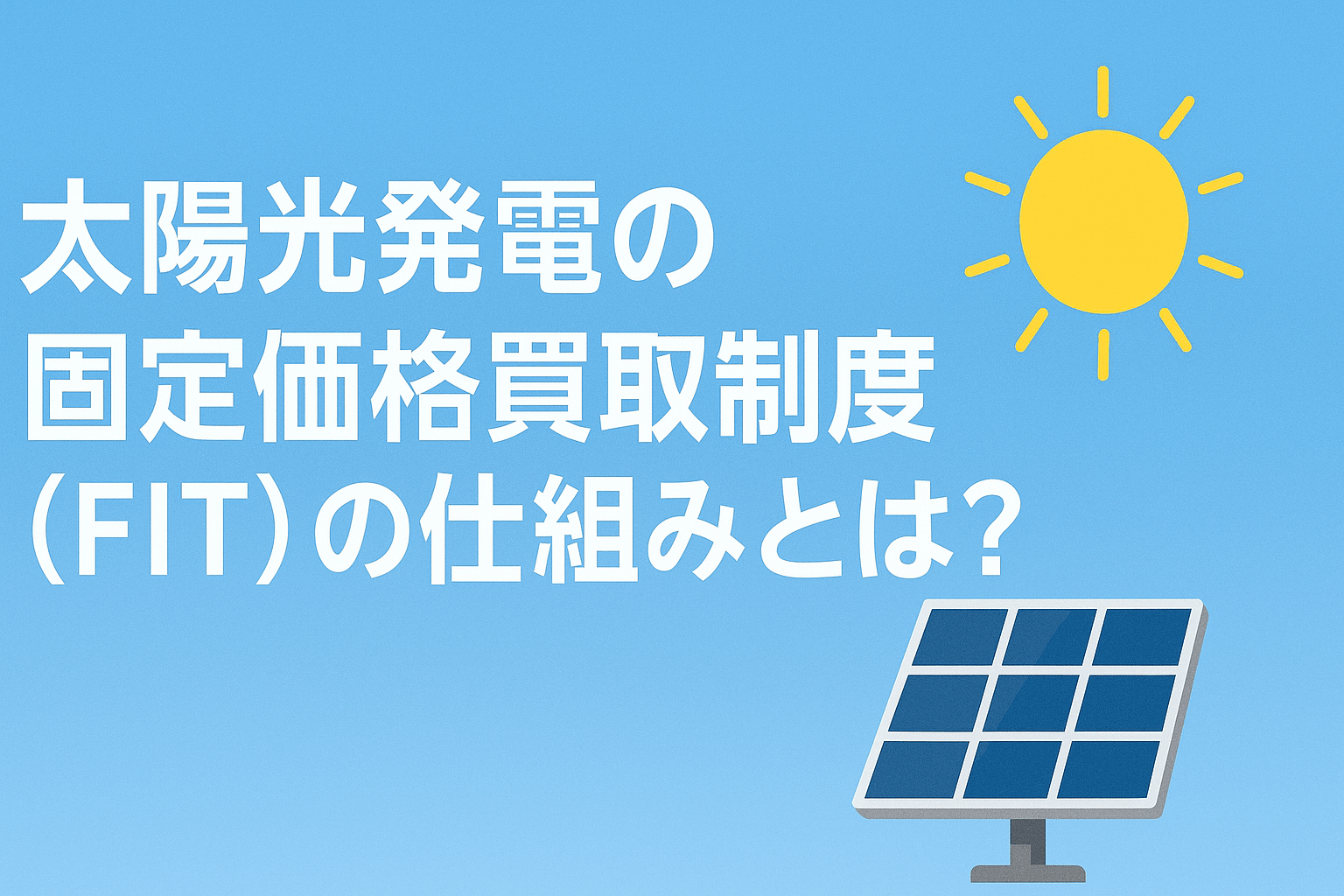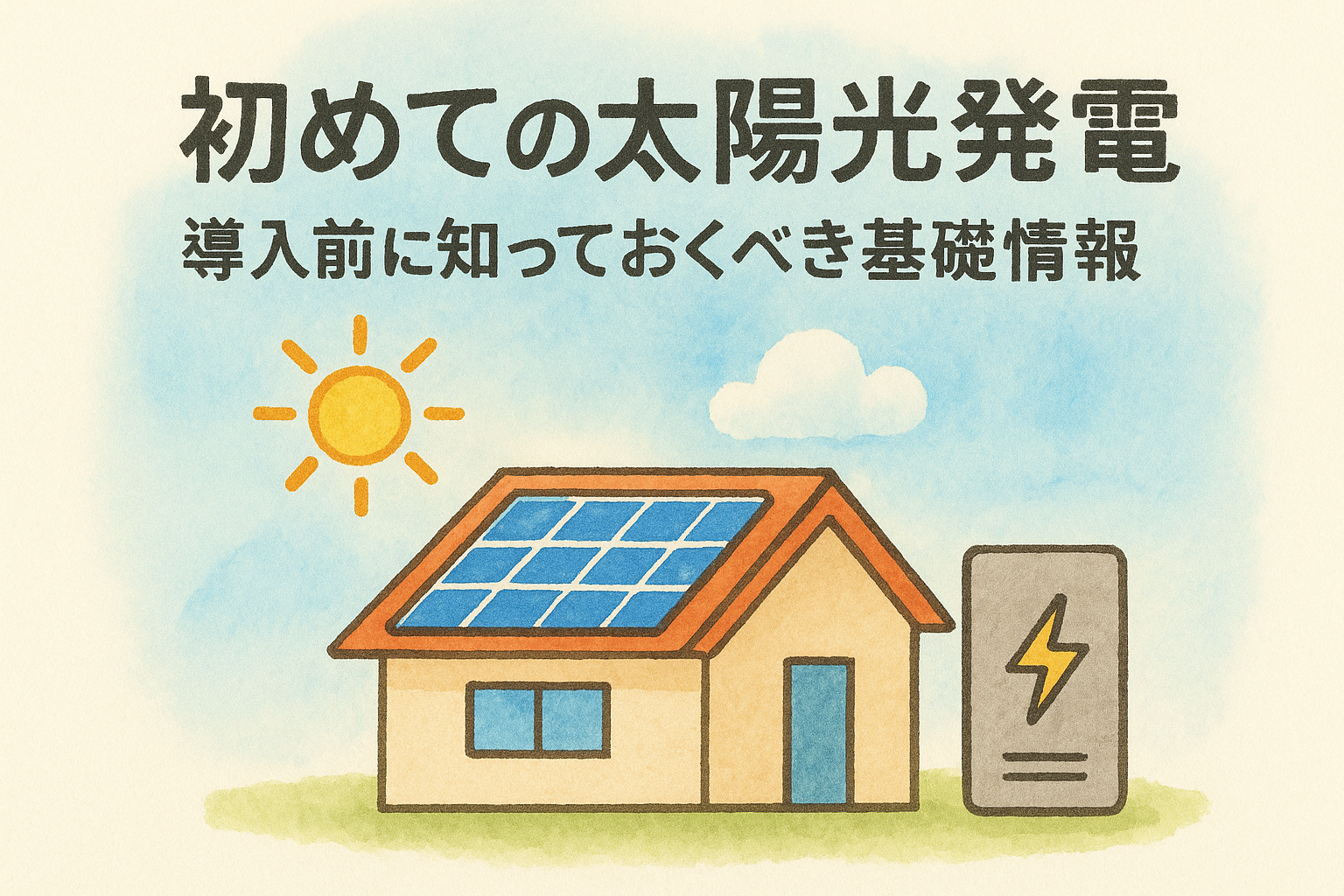太陽光発電で発電した電気の流れ
太陽光発電システムは、昼間に太陽の光を電気に変換します。発電した電気はまず家庭内の電力消費に使われ、それでも余った場合は電力会社に送られます。
この仕組みは自動的に制御されており、家庭側で特別な操作を行う必要はありません。
電気の流れを簡単に整理すると
-
太陽光パネルが太陽の光を受けて発電する
-
発電した直流電気をパワーコンディショナが交流に変換
-
家庭内の照明や家電に優先的に使用
-
使い切れず余った分は電力会社へ自動的に送電される
この仕組みによって、発電電力を無駄なく活かすことができます。家庭で使う電気を優先し、余剰電力は自動的に売る、というのが基本構造です。
売電とは?国の制度に基づく仕組み
太陽光発電によって生まれた電気を電力会社に売ることを売電と言います。売電には、国が定める固定価格買取制度(FIT)が関係しています。
FIT制度の概要
FIT制度は、再生可能エネルギーで発電した電力を一定期間、固定価格で電力会社が買い取る仕組みです。
この制度により、一般家庭でも発電した電気を収益化できるようになりました。
売電のルール
-
電力会社が国で定められた価格で電気を買い取る
-
家庭用(10キロワット未満)は余剰電力買取方式
-
買取期間は10年間
-
買取単価は設置年度で固定される
2025年時点では、住宅用太陽光の売電単価は1キロワット時あたりおよそ16円前後です。
FIT制度が始まった2012年当時は42円という高価格でしたが、導入コストの低下とともに単価も下がってきています。
売電のメリット
-
使わない電気を収益に変えられる
-
FIT制度により10年間は価格が固定され、安定した収入を得られる
-
電気代全体の支出を減らせる
売電のデメリット
-
FIT期間が終了すると買取価格が大幅に下がる
-
自家消費の方が経済的に有利なケースが増えている
-
買取期間が終わると契約更新手続きが必要
自家消費とは?家庭内で使う電気の活かし方
自家消費とは、太陽光で発電した電気をそのまま家庭内で使用することを指します。
電力会社から買う電気を減らせるため、電気代を直接削減できます。
自家消費のメリット
-
電気代の節約につながる
-
売電単価よりも買電単価の方が高いため、使う方が得になる
-
停電時にも発電電力を利用できる(蓄電池があれば夜間も使用可能)
-
環境負荷の少ない暮らしが実現できる
自家消費のデメリット
-
昼間に家を留守にしていると発電した電気を使い切れない
-
蓄電池を設置しないと夜間の電気使用に活かせない
-
発電量と消費量のバランスを取る必要がある
太陽光発電の経済性を高めるには、自家消費率を上げる工夫が重要です。
そのためには蓄電池やHEMS(家庭用エネルギーマネジメントシステム)の導入が効果的です。
売電と自家消費の違いと収益性比較
かつては「売電によって利益を得る」ことが主流でしたが、現在では電気料金の上昇により「自家消費の方が得」な傾向が強まっています。
売電と自家消費の比較表
| 比較項目 | 売電 | 自家消費 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 余剰電力を販売して収益を得る | 発電電力を使って電気代を節約する |
| 価格の目安 | 約16円(1kWhあたり) | 節約効果 約30円(買電単価換算) |
| メリット | 安定した収益を得られる | 節約効果が高い 停電時も安心 |
| デメリット | FIT終了後は単価下落 | 昼間に家を使わないと効果が薄い |
| おすすめの家庭 | 初期導入期 | 蓄電池や電気自動車を併用する家庭 |
電気料金の高騰を考慮すると、今は「使って節約する方が価値が高い」状況です。
そのため、これからの時代は売電と自家消費をうまく組み合わせるハイブリッド運用が主流になります。
自家消費率を高める具体的な方法
1. 蓄電池の導入
昼間に発電した電気を蓄電池にため、夜に使うことで自家消費率を上げられます。
容量6キロワット時から10キロワット時程度の蓄電池を導入すれば、一晩分の電気をまかなえることも可能です。
停電時にも使用できるため、災害対策としても価値があります。
2. 電気使用を昼間に集中させる
洗濯機や食洗機など、動作時間をタイマー設定できる家電を昼間に運転するようにすれば、発電電力を効率的に利用できます。
家事のタイミングを発電時間帯に合わせることが節約の第一歩です。
3. HEMSを活用してエネルギー管理
HEMSを導入すれば、家の中でどの機器がどれだけ電気を使っているかを把握できます。
リアルタイムでデータを見ながら無駄を減らし、発電と消費のバランスを最適化できます。
4. 電気自動車との連携
電気自動車を蓄電池として活用するV2Hシステムを導入すれば、昼間に充電し夜に家庭で使用することも可能です。
車と家の電力を連動させることで、より柔軟な自家消費運用が実現します。
卒FIT後のおすすめ運用
FIT制度の買取期間(10年間)が終了すると、売電単価はおよそ8円前後に下がります。
この時点では、売るよりも使う方が圧倒的にお得です。
卒FIT後の運用アイデア
-
蓄電池を導入して発電電力を家庭で最大限活用する
-
電力会社の再エネ買取プランを選び、有利な条件で売電する
-
地域のマイクログリッド(電力の地産地消ネットワーク)に参加する
さらに、多くの自治体では蓄電池導入や再エネ利用に関する補助金制度も設けられています。
補助制度を活用すれば、初期費用を大幅に削減することも可能です。
まとめ
太陽光発電で余った電気は、自宅で使うか、電力会社に売るかの二択です。
これまでの主流は売電による収益化でしたが、現在は電気代の上昇とFIT終了により、自家消費中心の考え方が主流に移りつつあります。
まとめると次の通りです。
-
売電は収益、自家消費は節約につながる
-
2025年以降は「使う方が得」な時代へ移行
-
蓄電池やHEMSの導入で自家消費率を高めることがポイント
太陽光発電は、発電するだけでなく「どう活かすか」が重要です。
発電した電気を自分の生活に合わせて上手に使うことで、より大きな経済的メリットと安心を得ることができます。