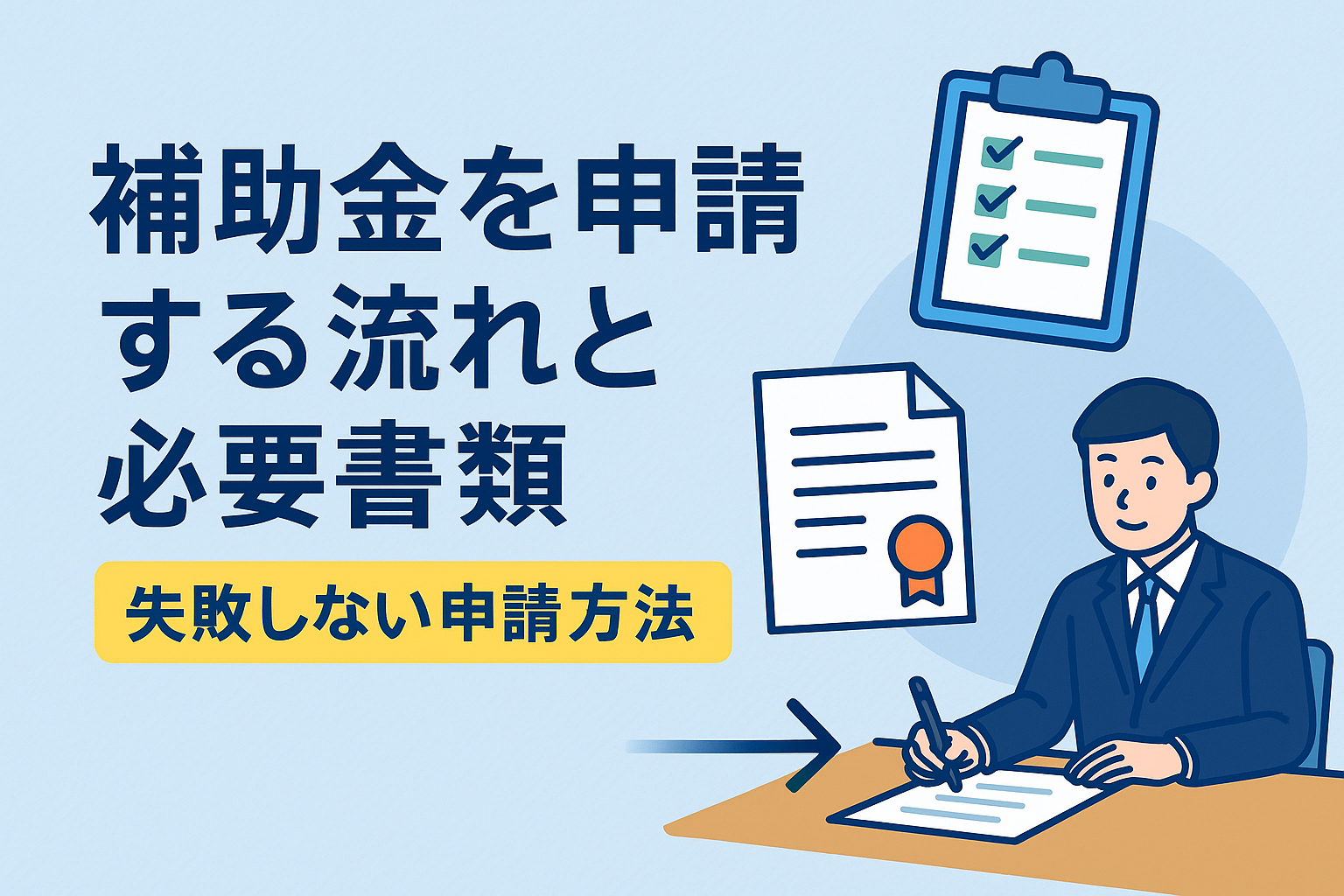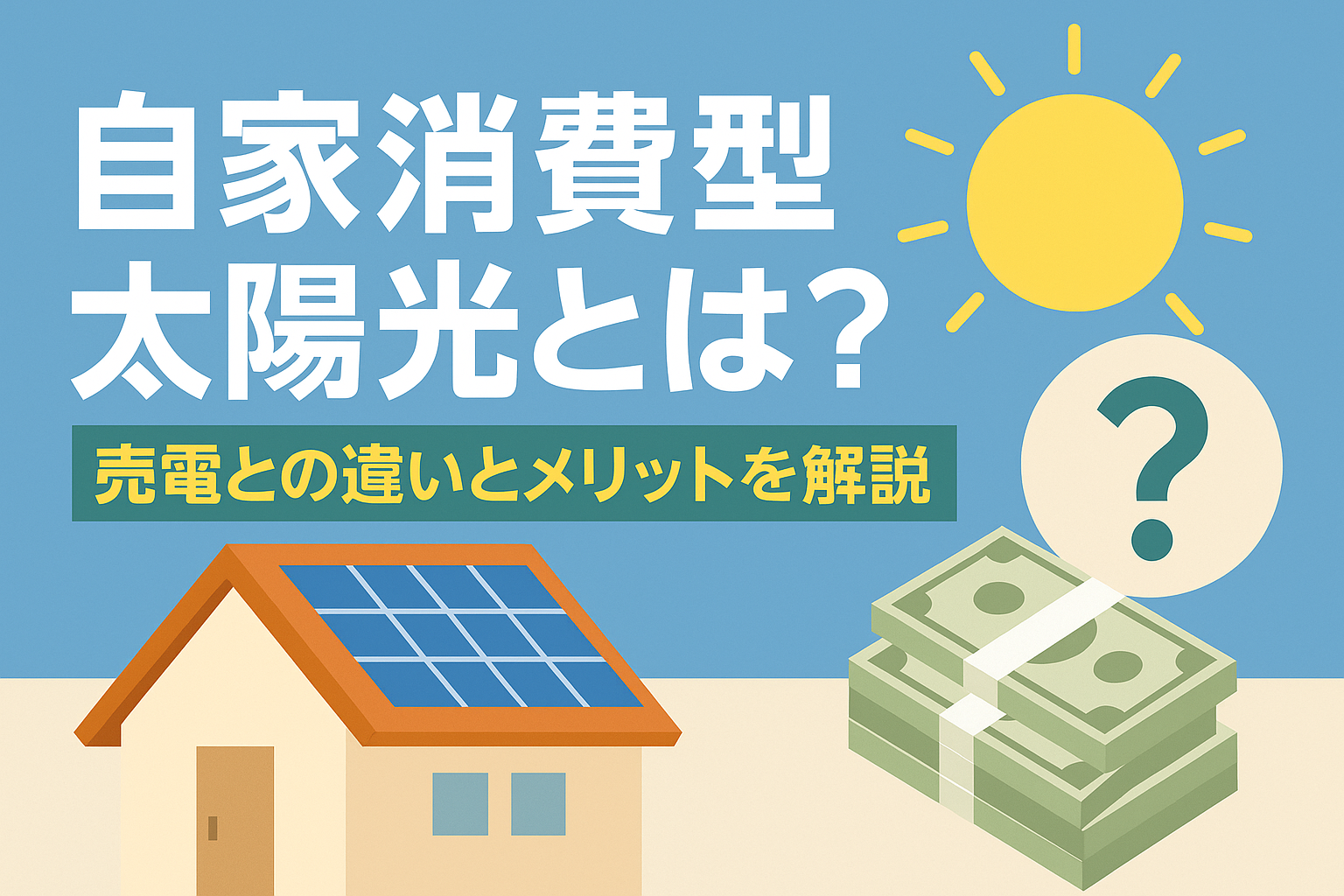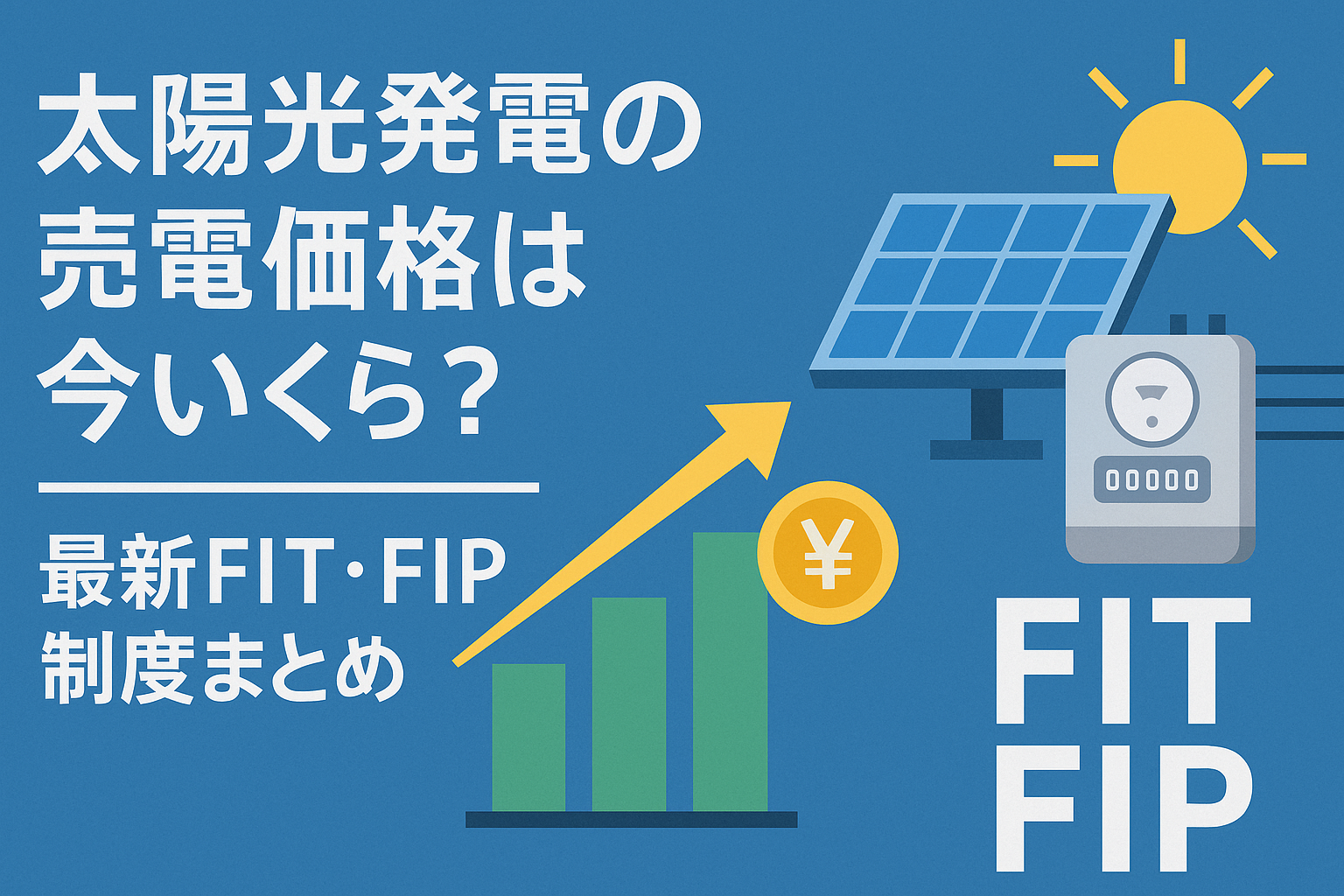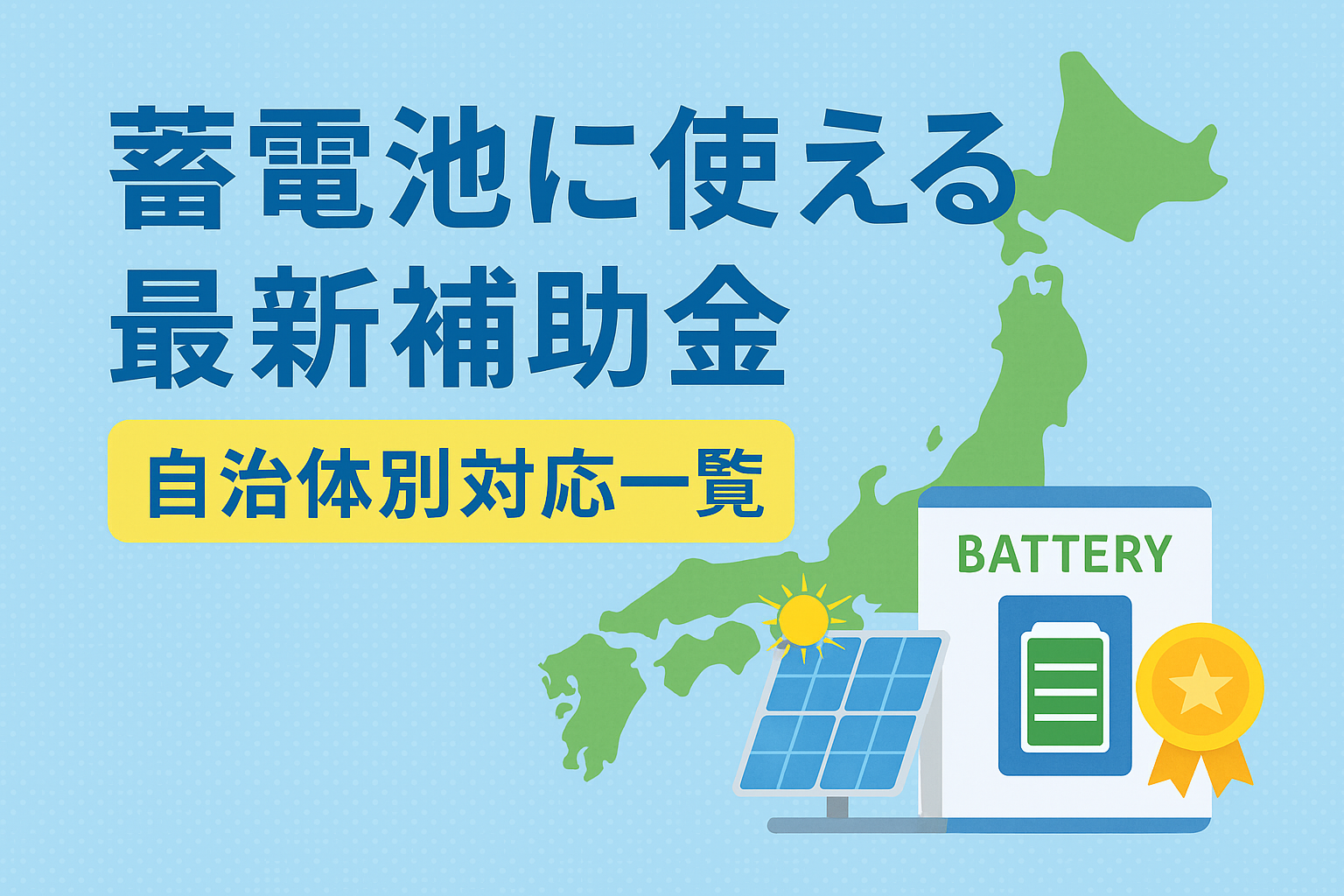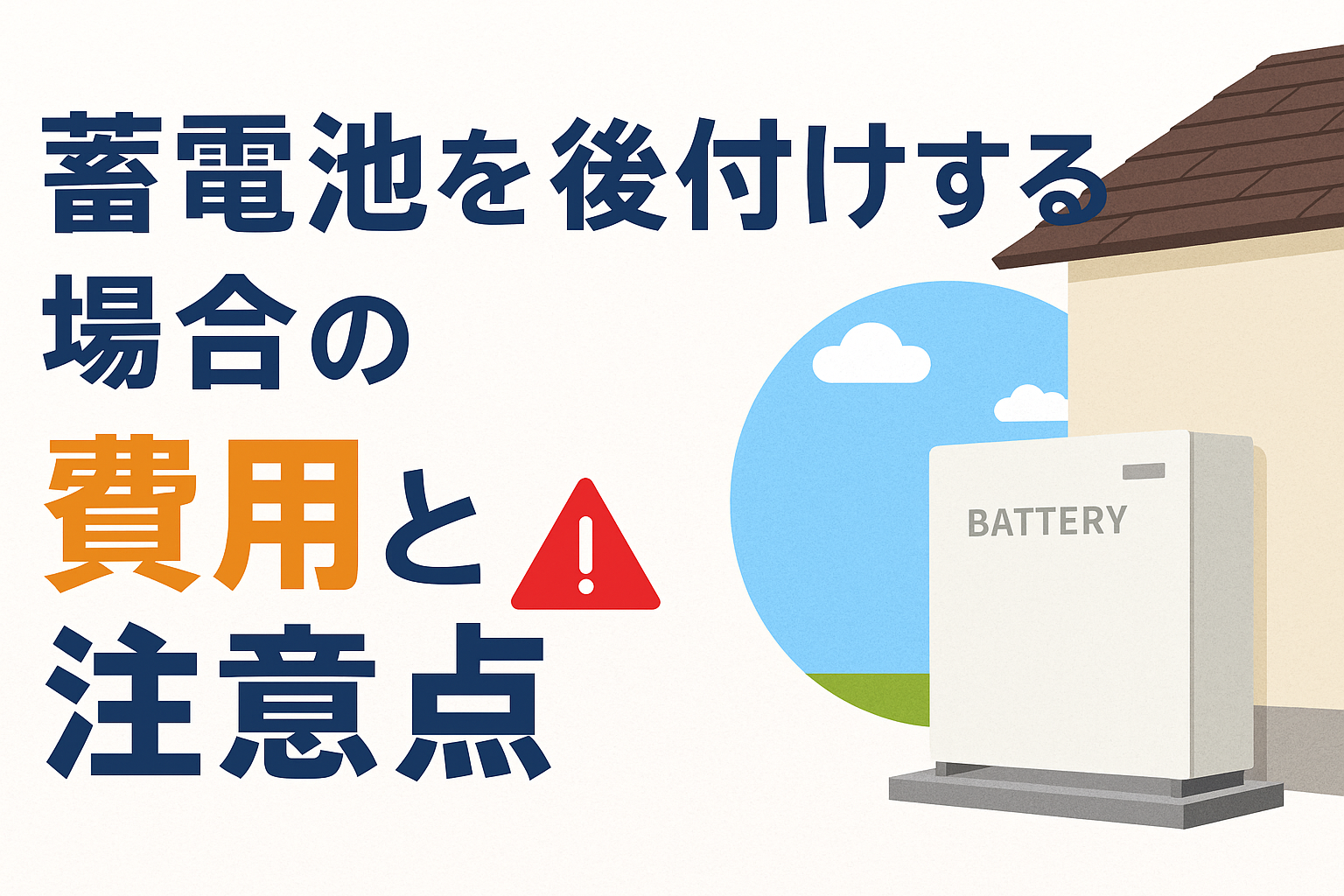本記事の読み方(先に結論)
-
太陽光だけでも、日中在宅の家庭なら**電気代を20〜40%**削減しやすい
-
太陽光+蓄電池(10kWh前後)なら**30〜60%**削減が狙える(自家消費率向上がカギ)
-
オール電化・電気自動車(EV)充電と相性抜群。夜間活用の設計次第で効果が跳ね上がる
-
回収目安は8〜12年。補助金・高騰する電気料金・売電単価低下を踏まえ、自家消費重視がベター
以下、前提条件→家族別ケース→プラン別比較→季節変動→投資回収まで、順を追って丁寧に見ていきます。
シミュレーション前提と用語の超要約
数値は「傾向を理解するための代表値」です。お住まい、屋根、プラン、使用状況で変動します。
-
電気料金:平均単価(燃調・再エネ賦課金含む)を30円/kWh(日中実効35円/kWh、夜間25円/kWh)で概算
-
売電単価(余剰):15円/kWh(住宅FITの代表的な水準を想定)
-
太陽光の年平均発電量:1kWあたり1,100kWh/年(関東〜関西の中庸値)
-
代表機器:太陽光5kW・7kW・10kW、蓄電池10kWh
-
自家消費率(太陽光のみ):30〜50%、蓄電池あり:50〜80%
-
用語メモ
-
自家消費:発電した電気を家でそのまま使うこと
-
余剰売電:使いきれなかった分を電力会社に売ること
-
稼働率・損失:季節差・機器損失(パワコン等)をざっくり内包
-
式の基本形
年間節約額 =(自家消費量 × 家庭の買電単価)+(売電量 × 売電単価)
ケースA:共働き・3人家族(昼間ほぼ不在)× 太陽光5kW
-
年間使用電力量:4,200kWh(350kWh/月)
-
太陽光発電:5kW × 1,100=5,500kWh/年
-
自家消費率(昼間不在が多い):35%想定 → 自家消費1,925kWh、売電3,575kWh
節約額(年)
-
自家消費分:1,925kWh × 30円 = 57,750円
-
売電分:3,575kWh × 15円 = 53,625円
-
合計:111,375円 ≒ 9,280円/月
ポイント
-
昼間不在でも「冷蔵庫・待機電力・タイマー洗濯・食洗機の昼稼働」で自家消費率を底上げ可能
-
売電で下支えされるが、蓄電池を入れると効果がさらに安定
ケースB:共働き・子ども2人(夕方〜夜ピーク)× 太陽光7kW+蓄電池10kWh
-
年間使用電力量:5,400kWh(450kWh/月)
-
太陽光発電:7kW × 1,100=7,700kWh/年
-
蓄電池で自家消費率を65%に向上 → 自家消費5,005kWh、売電2,695kWh
節約額(年)
-
自家消費:5,005kWh ×(昼夜平均単価30円のままでも)= 150,150円
-
実際は「昼の高単価を避け夜間活用」なので、実効効果は160,000円超になることが多い
-
-
売電:2,695kWh × 15円 = 40,425円
-
合計:約200,000円/年(≒16,700円/月)
ポイント
-
夕〜夜のピークを蓄電池でカバーし、買電ピークを削る設計が効く
-
食洗機・洗濯乾燥・風呂給湯などの負荷シフトがカギ
ケースC:5人家族・オール電化(給湯・調理が電気)× 太陽光10kW+蓄電池10kWh
-
年間使用電力量:7,800kWh(650kWh/月)
-
太陽光発電:10kW × 1,100=11,000kWh/年
-
自家消費率:70%(昼〜夜を蓄電でブリッジ)→ 自家消費7,700kWh、売電3,300kWh
節約額(年)
-
自家消費:7,700kWh × 30円 = 231,000円
-
オール電化は昼夜単価差や季節差が大きいので、実効で25〜35万円に振れる
-
-
売電:3,300kWh × 15円 = 49,500円
-
合計:約28〜30万円/年(≒23,000〜25,000円/月)
ポイント
-
太陽光10kWは屋根条件が前提。ヒートポンプ給湯(エコキュート)やEV充電との連携が効率的
-
冬季の給湯負荷対策に、昼間の沸き上げを設計へ組み込むと自家消費率UP
ケースD:テレワーク多め・ペットあり(昼間在宅)× 太陽光5kW+蓄電池なし
-
年間使用電力量:4,800kWh(400kWh/月)
-
太陽光発電:5,500kWh/年(5kW)
-
自家消費率:50%(在宅+空調+PC)→ 自家消費2,750kWh、売電2,750kWh
節約額(年)
-
自家消費:2,750kWh × 30円 = 82,500円
-
売電:2,750kWh × 15円 = 41,250円
-
合計:123,750円/年(≒10,300円/月)
ポイント
-
在宅はエアコン・空調・電子機器の昼利用で自家消費が伸びる
-
まずは太陽光のみでも効果を実感しやすいプロファイル
電気料金プラン別の「効き方」の違い
1)従量電灯(単価フラット)
-
日中も夜も単価差が小さい
-
太陽光のみでも「昼の買電を置き換え」やすく、わかりやすい節約
2)時間帯別(夜間安い)
-
売電単価<昼の買電単価が一般的
-
昼の自家消費価値が相対的に高い。蓄電池で「昼→夜」スライドの価値は料金差に依存
3)季節別変動・燃調高いとき
-
電気料金上昇局面では自家消費の価値が上がる
-
将来の値上げリスクヘッジとして自家消費戦略が合理的
太陽光だけ vs 太陽光+蓄電池の差(概念図 verbal)
-
太陽光のみ:昼に山型、夜は買電。余剰は売電
-
太陽光+蓄電池:昼の余剰を貯め、夜の買電を相殺。自家消費率が跳ね上がる
-
売電単価が下がる一方、買電単価の高止まりが続くほど、蓄電の価値が増す
季節変動・地域差の注意
-
発電は春〜初夏が好調。夏は高温でパネル効率が下がることも
-
冬は日照短く発電減。暖房・給湯の負荷増で自家消費の価値はむしろ上がる
-
地域差:1kWあたり年900〜1,300kWh程度のレンジで変動。屋根方位・影・勾配が重要
EV(電気自動車)充電と組み合わせた伸びしろ
-
昼間太陽光→日中在宅充電で自家消費率がさらに上がる
-
夜間充電は安い時間帯を狙う。蓄電池経由のMIXができるとピークカットに有効
-
走行1,000km/月前後なら、電気代とガソリン代差でトータル節約が顕著に
光熱費だけじゃない副次効果
-
停電時の安心(非常用回路・全負荷型の違いを要確認)
-
CO₂削減・環境教育・資産価値向上(屋根・外観との調和設計が大切)
-
HEMSによる見える化で節電意識が定着
導入費用と回収イメージ(ざっくり版)
-
太陽光5kW:130〜150万円/年削減10〜13万円 → 回収10〜12年
-
太陽光7kW+蓄電池10kWh:280〜330万円/年削減18〜22万円 → 回収12〜15年
-
太陽光10kW+蓄電池10kWh(オール電化):350〜420万円/年削減25〜30万円 → 回収12〜14年
※ 補助金(自治体・蓄電池)で**−10〜150万円**程度の軽減も。屋根や配線条件で増減
「わが家はどれくらい下がる?」5分でざっくり計算
-
年間使用量(kWh)を明細で確認
-
太陽光容量(kW)×1,100=年間発電量を概算
-
自家消費率を見積もり(太陽光のみ30〜50%、+蓄電池50〜80%)
-
節約額=(自家消費量×買電単価)+(売電量×売電単価)
-
月割りし、ローン返済(ある場合)と差し引きで実質の月次インパクトを見る
例:年間5,400kWh・7kW・蓄電池あり・自家消費65%
-
発電7,700kWh → 自家消費5,005kWh、売電2,695kWh
-
買電30円、売電15円 → 年約200,000円の削減
-
ローン月15,000円なら、電気代削減(約16,700円)で相殺に近い設計も可
よくある疑問Q&A
Q1:共働きで昼不在。蓄電池なしでも入れる意味ある?
A:あります。待機負荷や昼のタイマー運転で自家消費化。売電も下支え。さらに効果を伸ばすなら蓄電池や運転シフトを検討。
Q2:売電単価が下がると損では?
A:今は買電単価>売電単価が一般的。だからこそ自家消費率UPがカギ。売るより使う設計が合理的。
Q3:冬の発電が少ないのが不安
A:冬は給湯・暖房で需要が増えるので、昼の自家消費価値はむしろ高い。エコキュート昼沸き上げ等で効果が出る。
Q4:メンテ費も入れるべき?
A:はい。点検・清掃は数年で数万円、パワコンは10〜15年で交換20〜40万円想定。長期の実質効果で評価しましょう。
Q5:どの容量がベスト?
A:屋根・契約・生活パターン次第。**「日中の負荷+夜の重要家電」**をどこまで賄いたいか、から逆算が王道。
導入を成功させる3つの設計ポイント
-
ライフログ化:洗濯・食洗機・給湯の時間帯を1週間メモ。昼シフト余地を見える化
-
機器連携:太陽光×蓄電池×エコキュート×EV×HEMSを一体設計。無駄を削る
-
将来前提:電気料金上振れ・家族構成の変化・EV導入予定まで見据えて容量を決める
実例まとめ(早見表)
| 家族像/機器 | 使用量/年 | 太陽光 | 蓄電池 | 自家消費率 | 年間節約目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:3人 昼不在多い | 4,200kWh | 5kW | なし | 35% | 約11万円 |
| B:4人 夕夜ピーク | 5,400kWh | 7kW | 10kWh | 65% | 約20万円 |
| C:5人 オール電化 | 7,800kWh | 10kW | 10kWh | 70% | 約28〜30万円 |
| D:在宅多め | 4,800kWh | 5kW | なし | 50% | 約12万円 |
※ 実住環境で±20%程度のブレは普通に出ます。見積り時は個別シミュ必須。
ここまで読んだら、次にやること
-
電気明細(12か月分)を用意
-
屋根の向き・影・勾配をチェック(図面やGoogleマップでも可)
-
「太陽光のみ」「太陽光+蓄電池」2案で試算
-
一括見積もりで複数社比較(売電前提ではなく自家消費前提で提案依頼がコツ)
-
補助金(自治体・蓄電池)を確認し、回収年数を再計算
まとめ
-
売電収益が細る時代は、自家消費こそ主役
-
太陽光のみでも月1万円前後、蓄電池ありなら月1.5〜2.5万円規模の削減が十分射程
-
オール電化・EV・エコキュートとの連携で、設計次第の伸びしろは大きい
-
本記事の代表値をベースに、あなたの家計実態で個別最適化すれば、投資効果はさらに明確になります