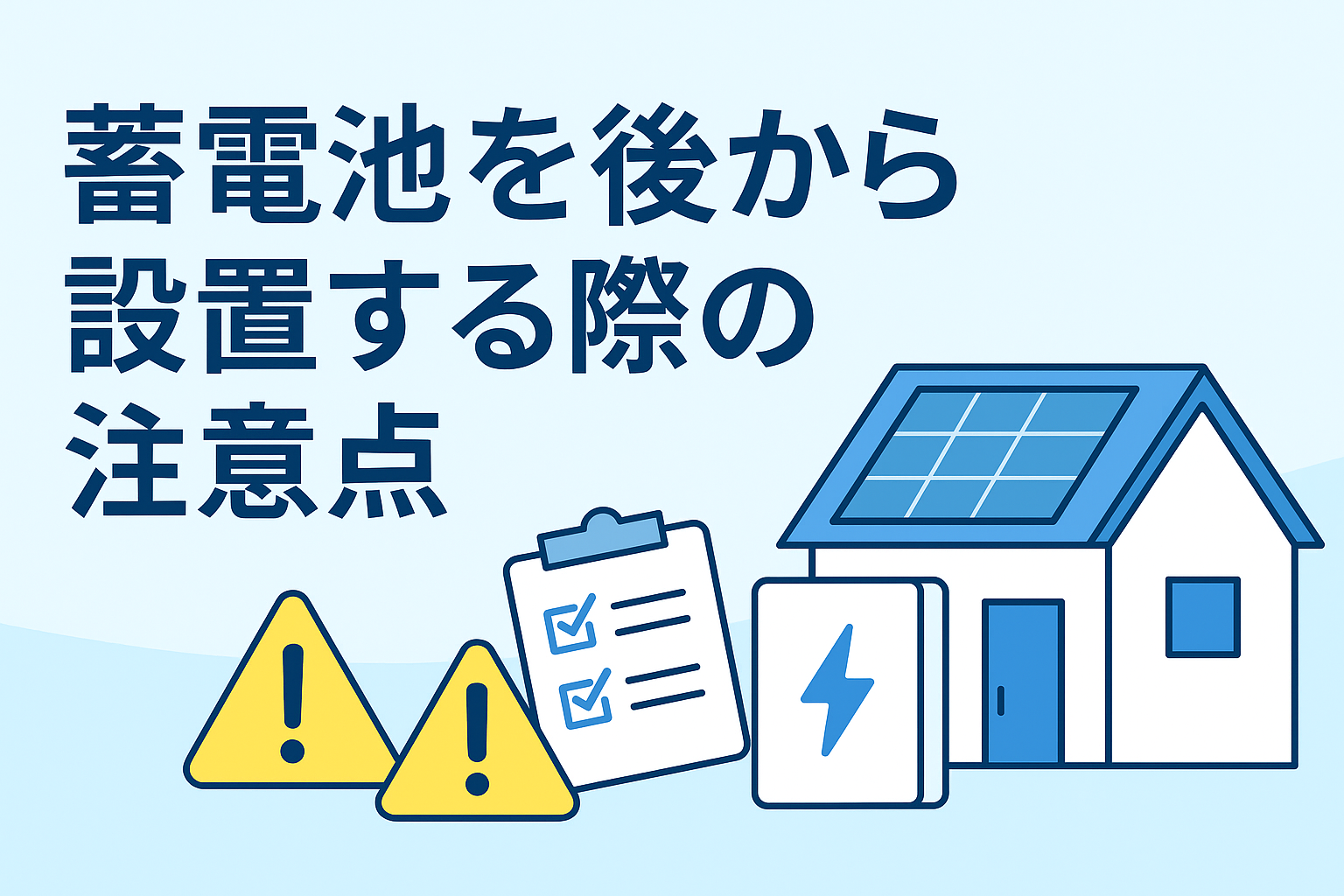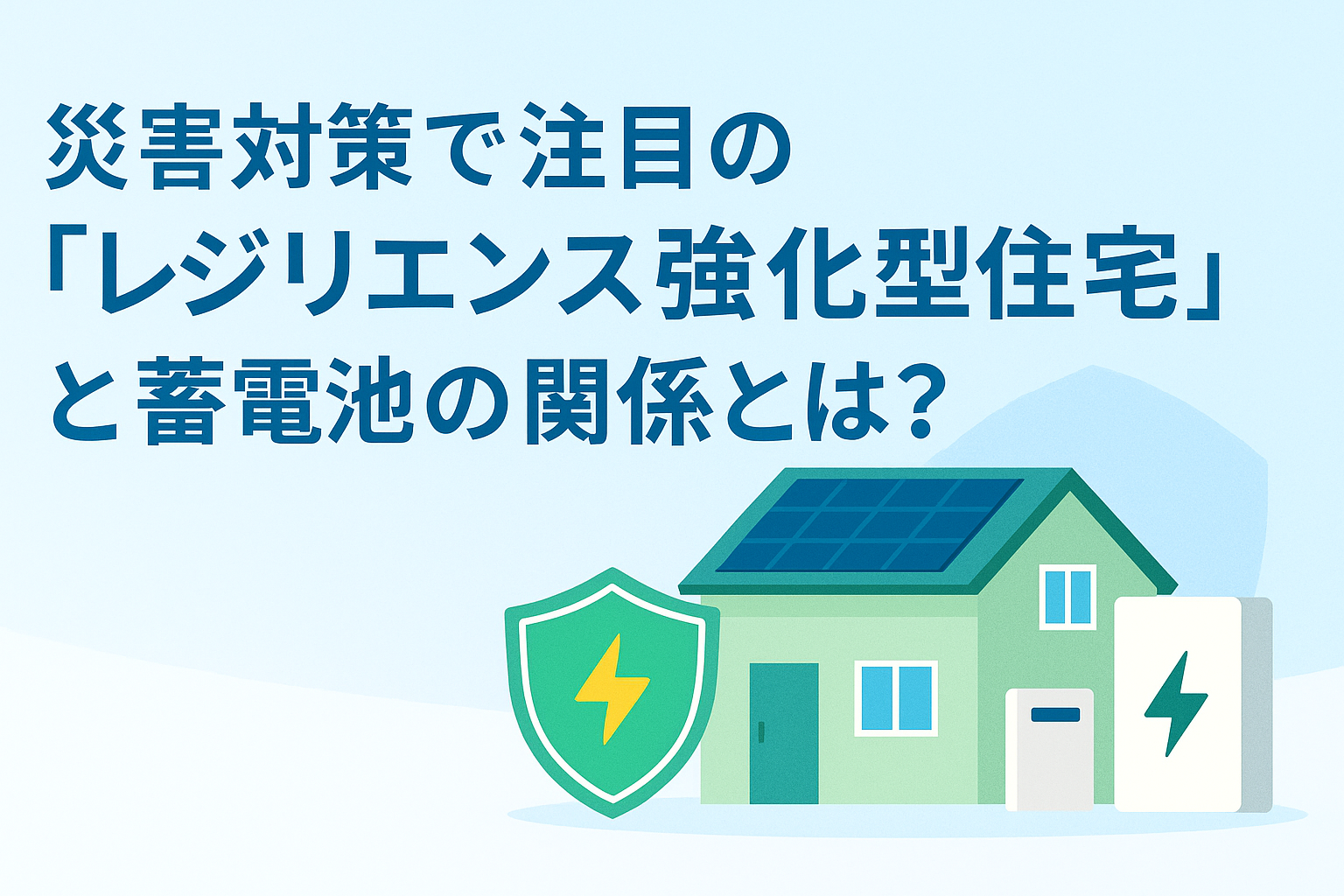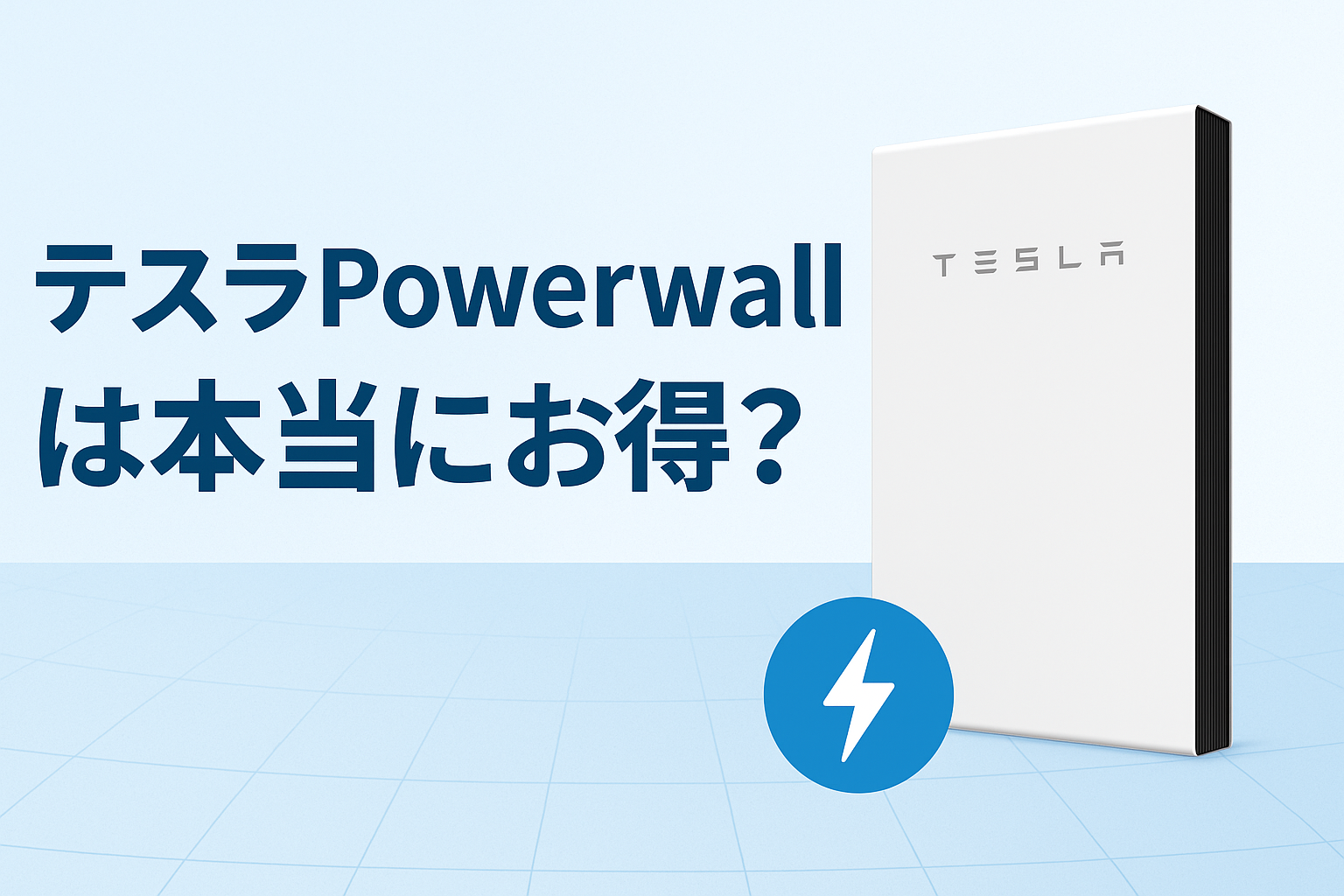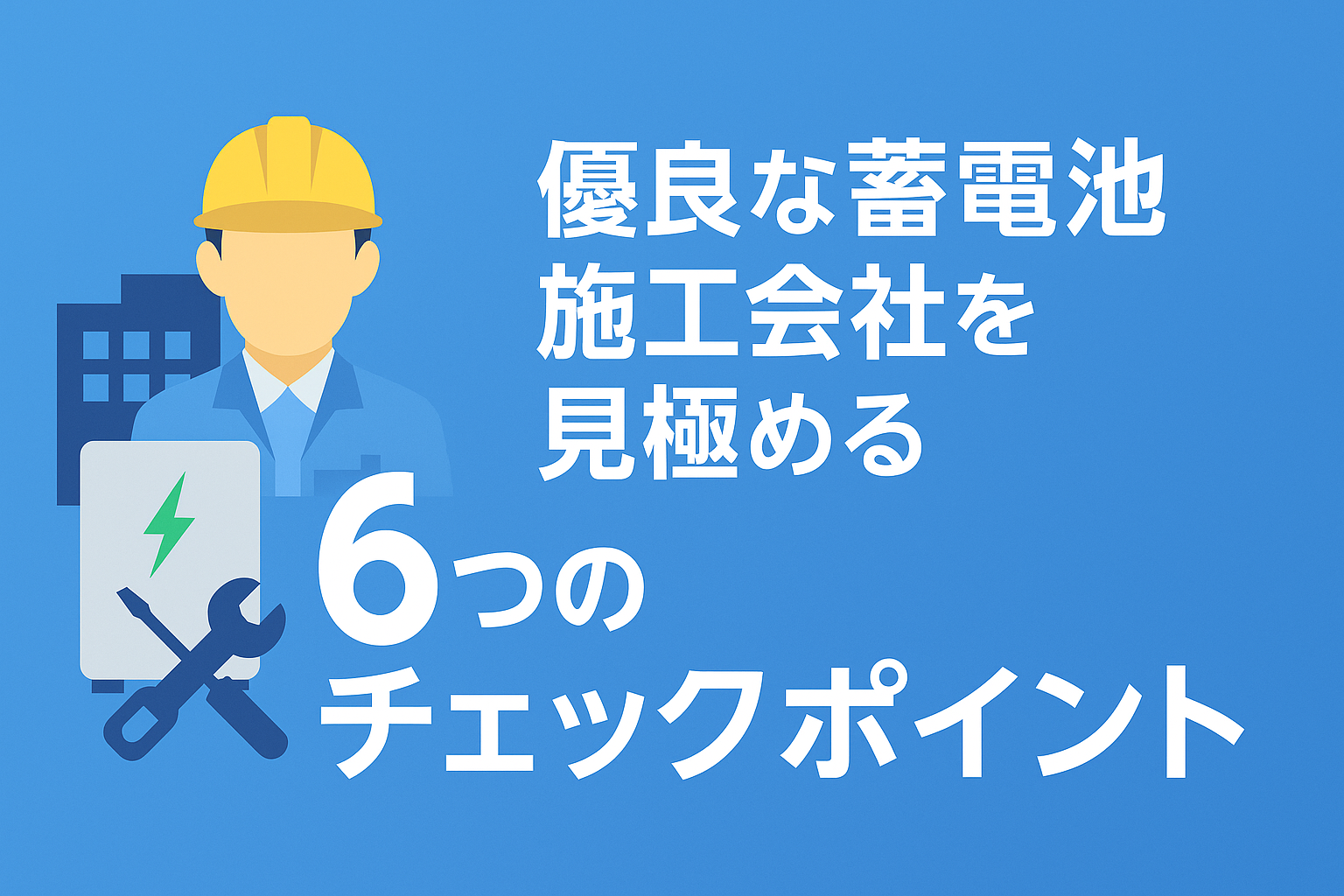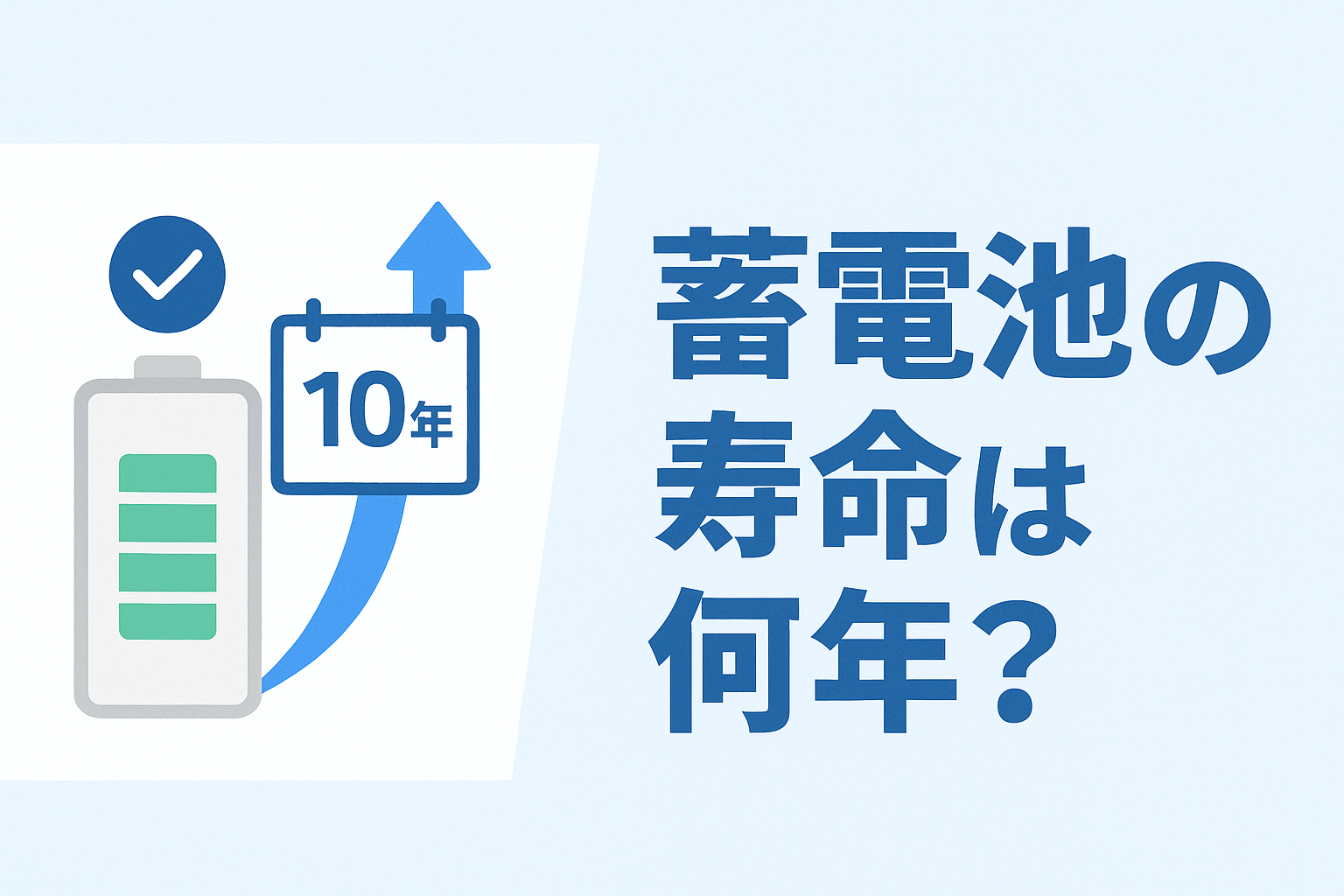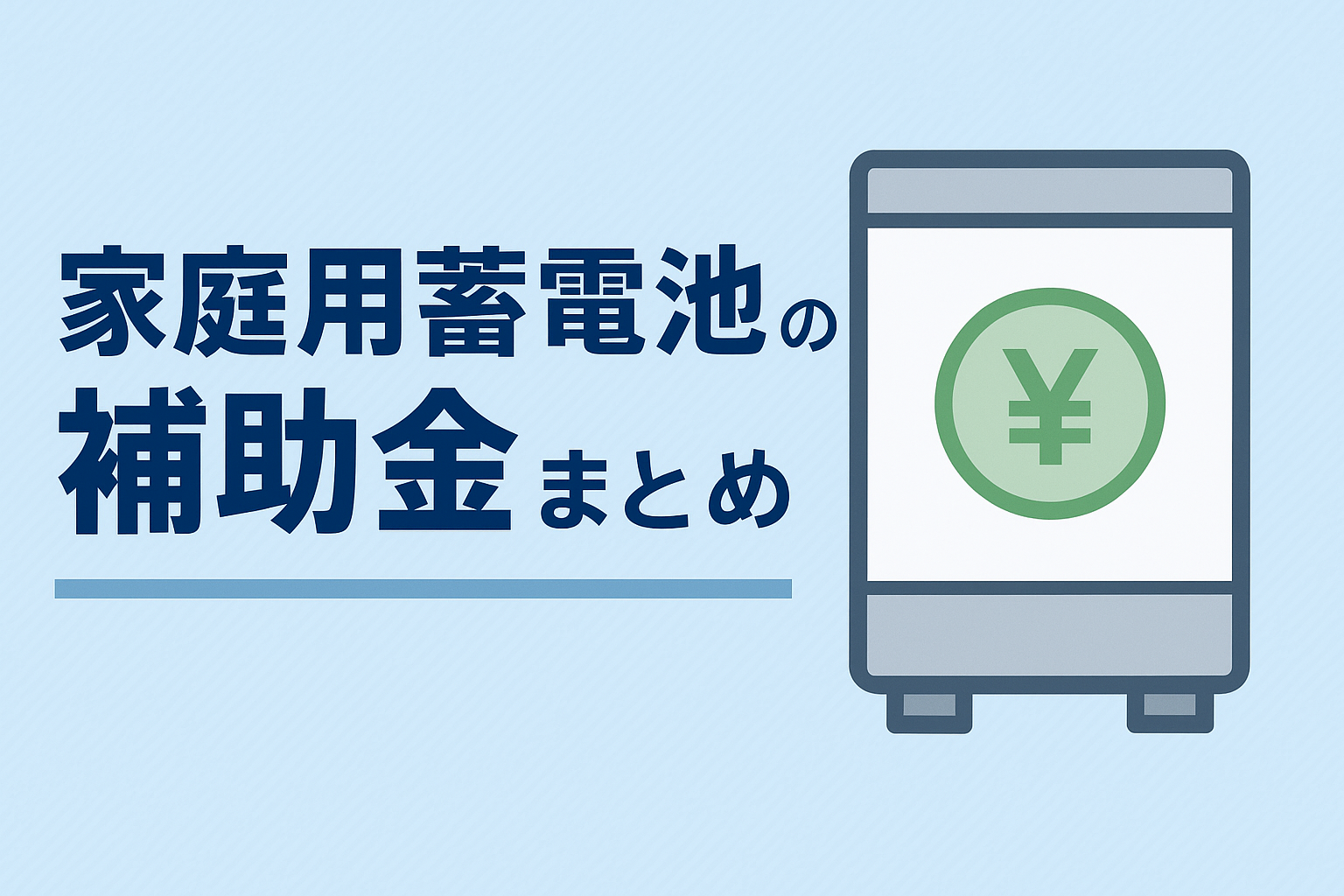はじめに|「あとから蓄電池を設置したい」はアリ?
太陽光発電の導入時に「とりあえずパネルだけ」「蓄電池はあとで…」と考える方は多いですが、
実は“あとから設置”には落とし穴も存在します。
この記事では、後付け蓄電池のメリット・デメリット、後悔しないための選び方やタイミングを徹底解説します。
後付けできるの?蓄電池の設置条件
蓄電池は基本的に後からの設置が可能です。
ただし、以下のような条件を事前に確認しておく必要があります。
- 既存の太陽光発電設備との連携可否
- 設置スペースの確保(屋内or屋外)
- 分電盤・配線の確認
- 電力契約や分譲マンションでの管理組合の許可
→ 特に、**太陽光のメーカーによっては「純正蓄電池しか接続できない」**こともあるため要注意です。
後から設置するメリット・デメリット
メリット
- 導入コストを分けられる(初期費用を抑えられる)
- 技術の進化を待てる(数年後の高性能モデルを選べる)
- 補助金制度のタイミングを狙える
デメリット
- 配線や工事が追加で必要になる
- 機種の選択肢が制限されることもある
- 太陽光と蓄電池の保証期間がバラバラになる
→ 費用面ではやや高くなるケースもあるため、長期的に考えてコスト比較が必要です。
後悔しない「後付け蓄電池」の選び方3ポイント
- ハイブリッド型か単独型かを確認
→ ハイブリッド型は太陽光と連携して効率的だが、互換性に注意。 - 将来設置を想定した太陽光業者を選んでおく
→ 導入時に「蓄電池も視野に入れている」と伝えておくと◎ - 地域の補助金タイミングを狙う
→ 例:東京都・神奈川県では2025年度中に再開予定
こんな人は“今すぐ”蓄電池の検討を!
- FIT終了(売電終了)から1〜3年以内の方
- 停電対策や子育て・高齢者との同居で電力確保が重要なご家庭
- 太陽光導入時に「蓄電池を後で」と考えていた方
→ 今なら自治体補助金も多数出ているため、設置タイミングとしては最適です。
まとめ|「あとから」でも遅くはない。今が再検討のベストタイミング
蓄電池の後付けは決して悪い選択ではありません。
しかし、設置タイミングと工事内容、補助金を正しく押さえることが重要です。
エネミツでは、後付けに対応した機種や工事ノウハウを持つ優良業者のみをご紹介しています。
不安や疑問がある方は、まずは無料相談をご活用ください。
✅【無料】後付けに対応した蓄電池を比較する
【CTAボタン】「後付けOKの優良業者に一括見積もり」