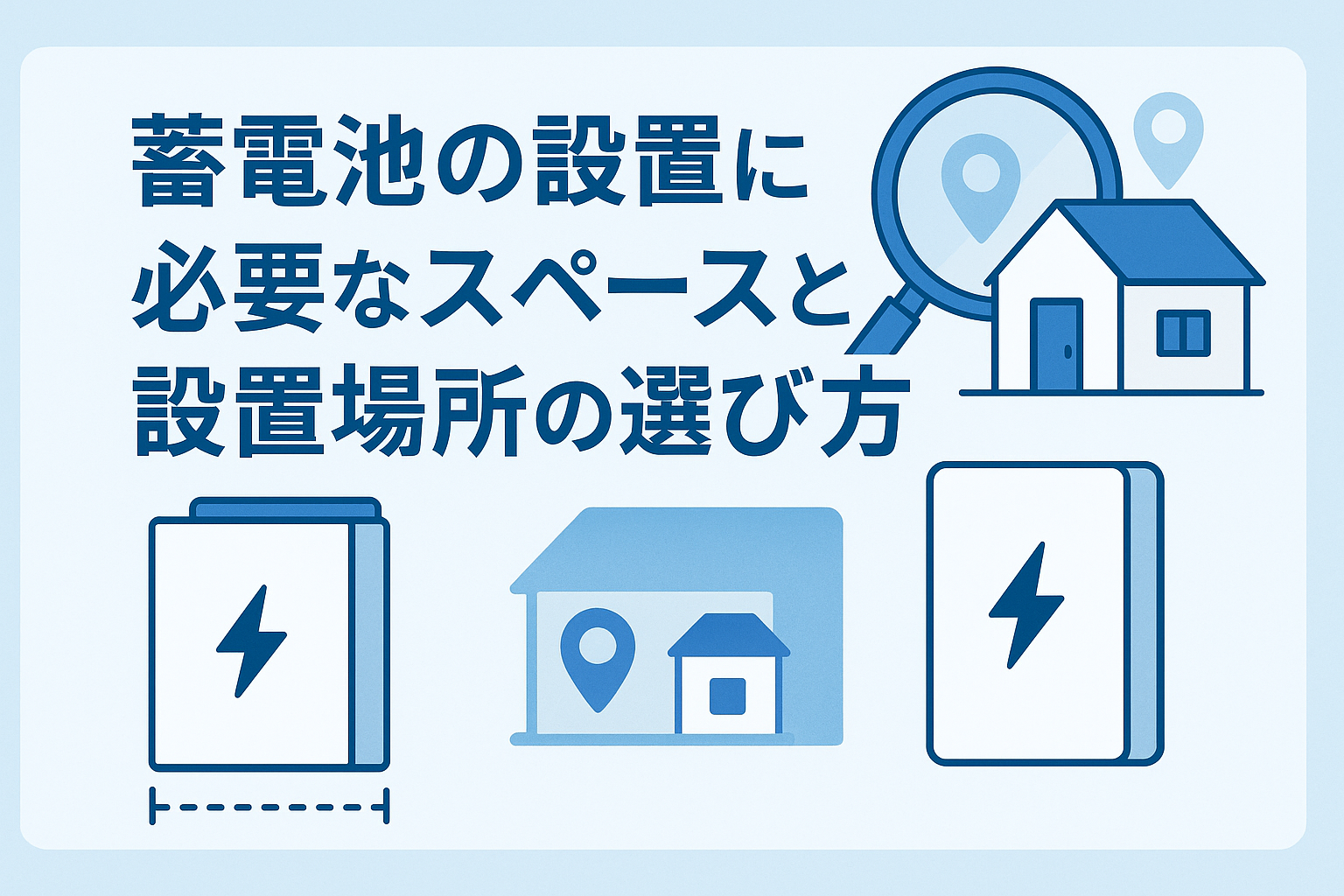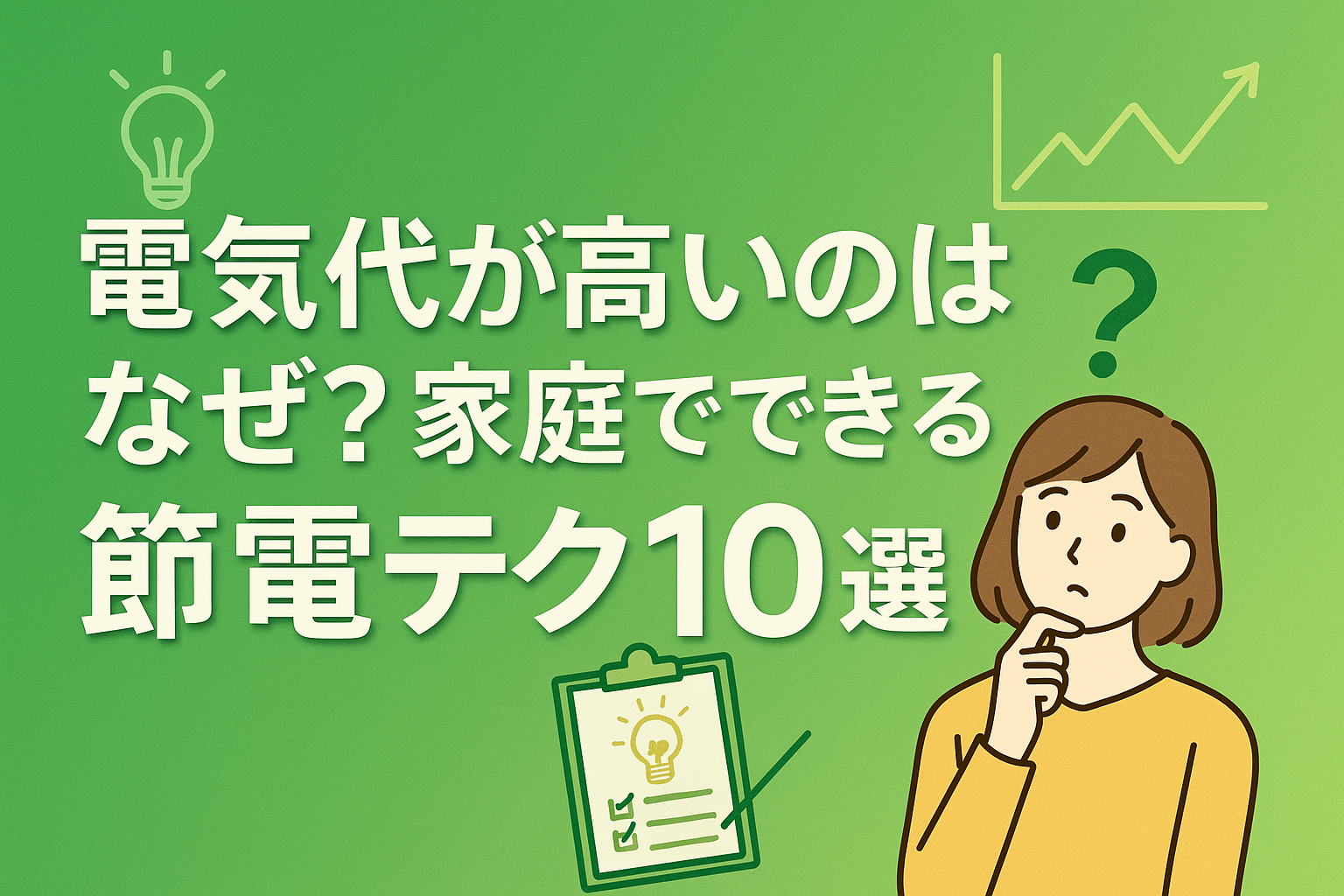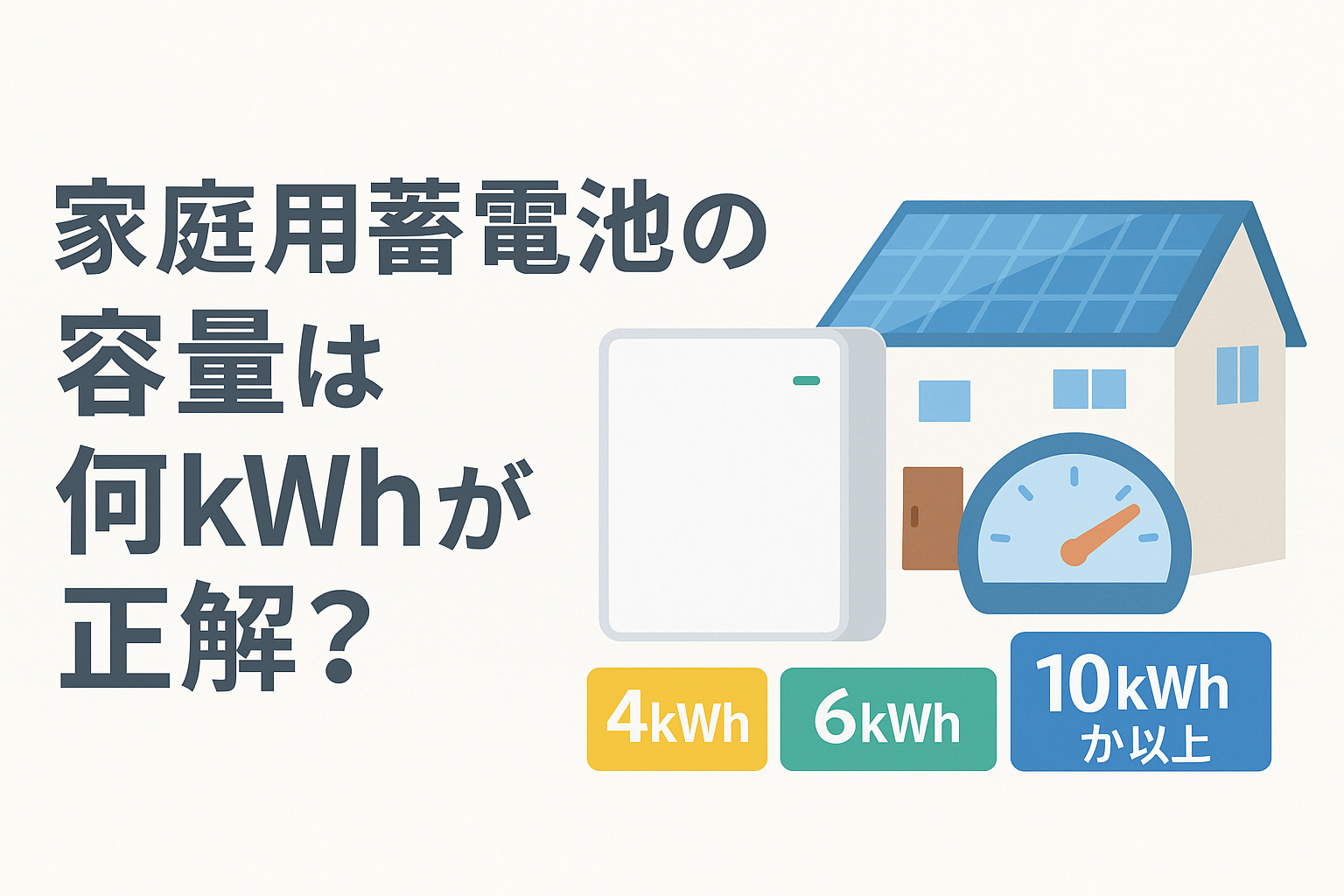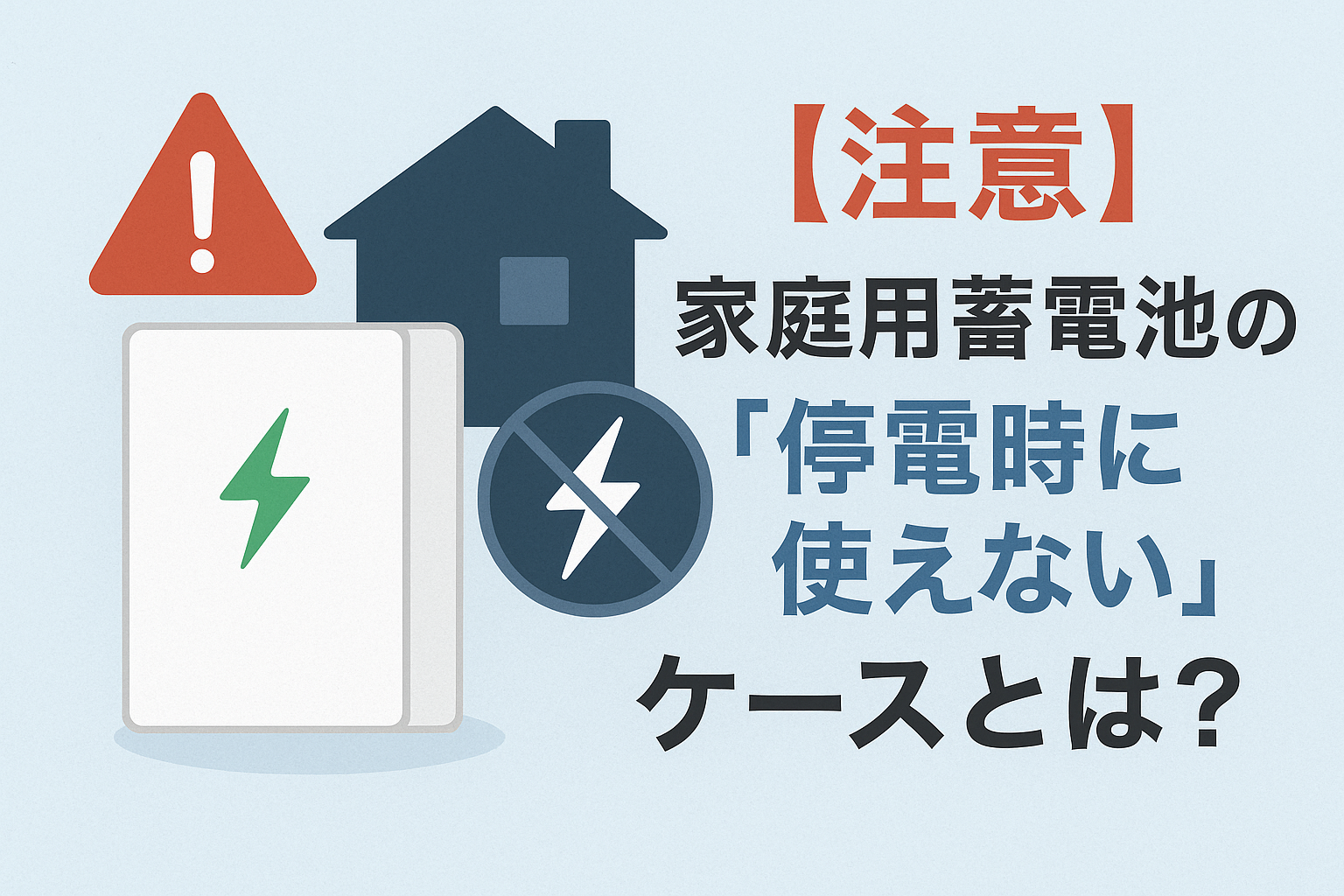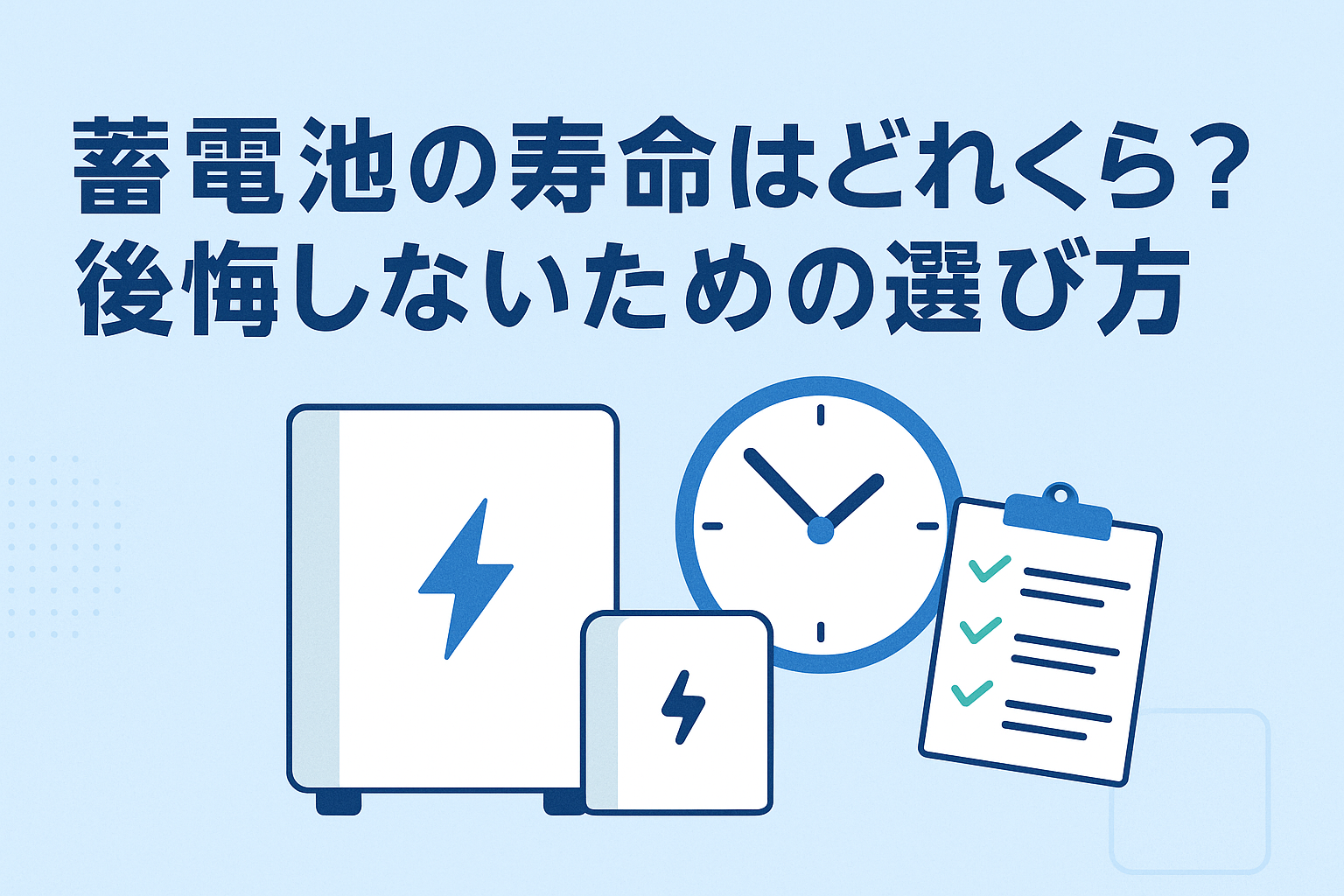[画像]
設置して終わりじゃない?気になるメンテナンス事情
太陽光発電を導入した方や検討中の方からよく寄せられる質問のひとつが、「メンテナンスって必要なんですか?」というもの。
実は、発電効率を保つためには定期的なチェックや清掃が重要です。
今回は、太陽光発電のメンテナンスの必要性、費用相場、頻度について詳しく解説します。
[画像]
結論:基本的にメンテナンスは必要です
太陽光パネルは屋外に設置され、雨風やほこり、鳥のフン、落ち葉など様々な影響を受けます。
これらが表面にたまることで発電効率が落ちる可能性があります。
また、接続部分の劣化やパワーコンディショナの故障など、見えない部分の異常に気づくのは難しいため、プロによる定期点検が推奨されています。
[画像]
メンテナンスの種類と頻度の目安
1. 日常的なチェック(年1回程度)
- パネル表面の汚れや割れがないか目視確認
- 発電量のチェック(急な低下がないか)
2. プロによる点検(4年に1回程度)
- 電気系統や配線の点検
- パワコンの動作確認
- 接地抵抗の測定(法的義務あり)
※経済産業省は4年に1回の点検を推奨しています(住宅用の場合)
[画像]
メンテナンス費用の相場
- 点検費用:1回あたり15,000〜30,000円程度
- 清掃費用:パネル1枚あたり1,000〜2,000円(高所作業費別)
- パワコン交換:10〜15年目で15〜30万円程度の交換が必要になることも
これらの費用を踏まえて、長期的なコストを見積もることが重要です。
[画像]
メンテナンス契約は必要?
太陽光発電の導入時に「メンテナンスパック」の契約を勧められることがあります。
月額数百円〜の内容で、年1回の点検やトラブル対応がセットになっているものも。
費用対効果や補償内容を確認しながら選ぶことが大切です。
[画像]
まとめ|“売ったら終わり”じゃない業者を選ぶのが大事
- メンテナンスは効率維持と安全のために重要
- 法定点検も含め、4年に1回はプロのチェックが理想
- 導入時のプランで「定期点検込みかどうか」も確認を
エネミツでは、販売後のサポート体制がしっかりした優良業者のみをご紹介しています。
「メンテナンス費用まで見積もって比較したい」などのご希望も、お気軽にご相談ください。
[画像]